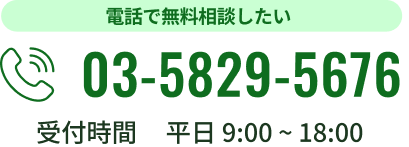個人再生とは?手続きの条件からメリット、任意整理との違いを解説
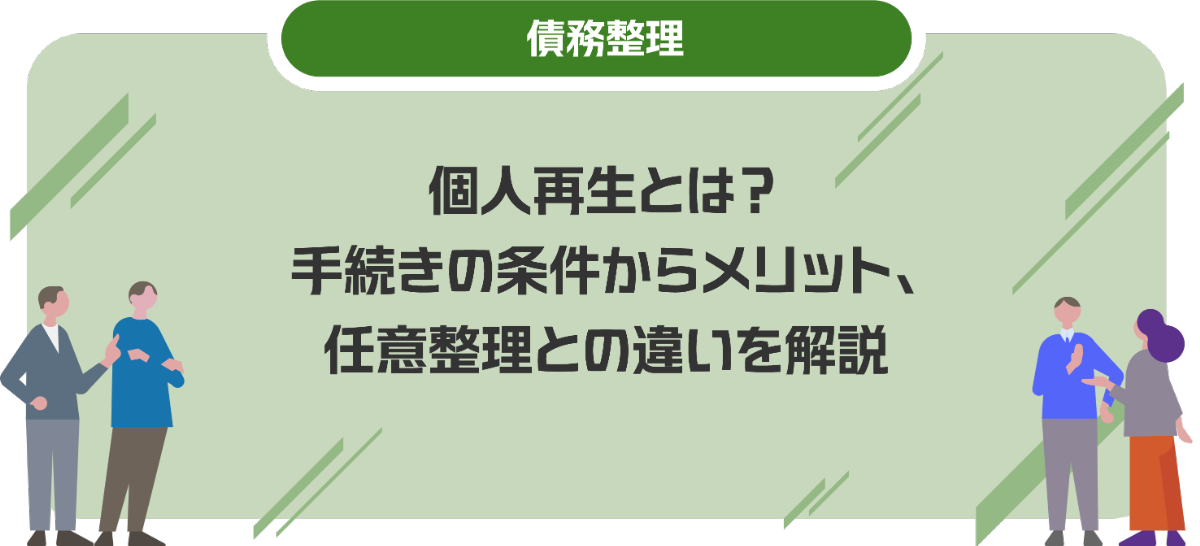
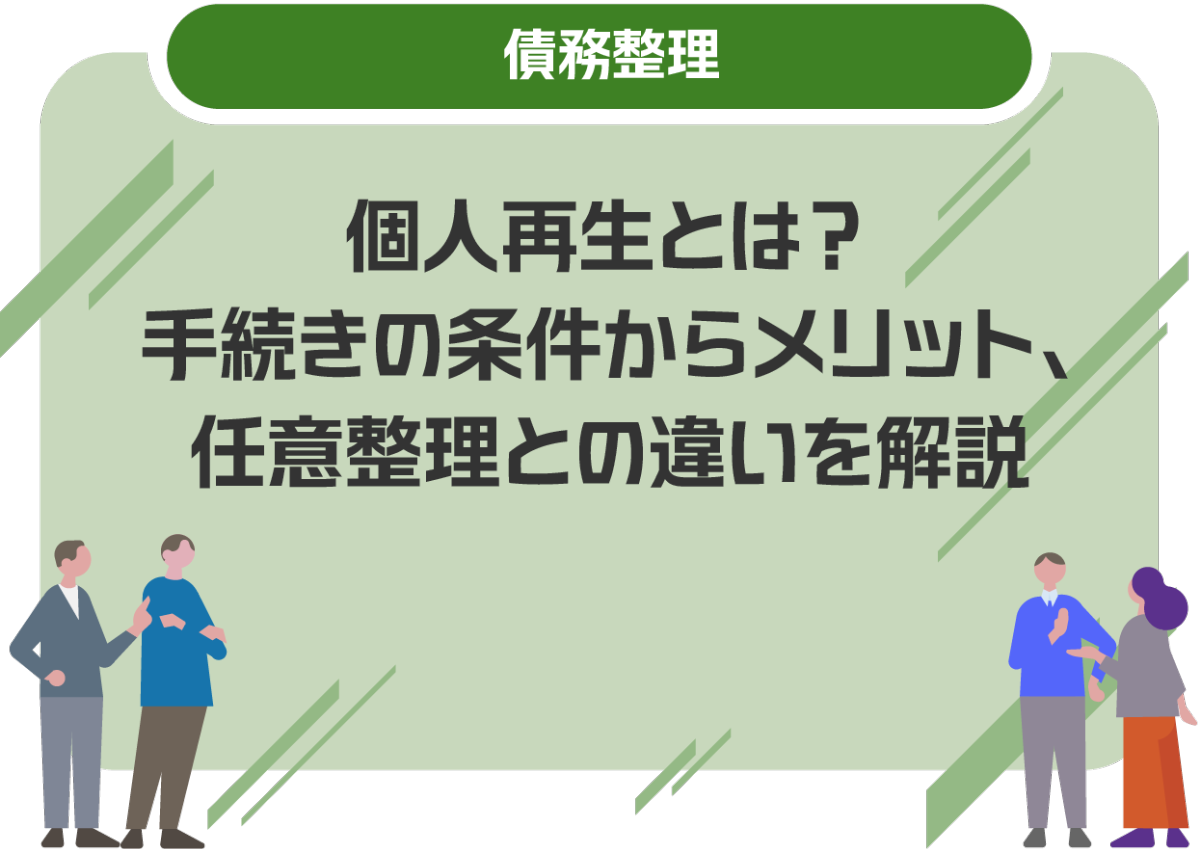
「毎月の返済に追われて生活が苦しいから、借金を減額させたい…」
そんな悩みをお持ちの方に最適な債務整理の方法が「個人再生」です。
この記事では、個人再生とはどのような手続きなのか、わかりやすく解説します。
個人再生のメリット・デメリットや他の債務整理方法との違いまで解説しているので、自分にあった債務整理方法が個人再生なのかどうかも分かるでしょう。
個人再生とは住宅などの財産を残したまま借金を大幅に減らすことができる手続きである
個人再生とは、借金を抱えて生活が苦しくなった人が、裁判所を通して借金を大幅に減額してもらい、残りの借金を3~5年かけて返済していく手続きです。
借金が返済できず生活が苦しくなった人が、経済的にやり直すための債務整理というカテゴリーの中の1つという認識で問題ありません。
個人再生の特徴として「住宅などの財産を手元に残したまま、借金を大幅に減らすことができる」点が挙げられます。
そのため、個人再生は
- 任意整理では返済が難しいほど多額の借金を抱えている方
- 住宅などの大切な財産を手放したくない
- 浪費やギャンブルが原因の借金に悩んでいる
という場合に有効な手段です。
個人再生の条件
個人再生を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下のとおりです。
- 債務総額が5,000万円以下であること
- 将来的に継続的または反復して収入を得る見込みがあること
個人再生には2種類の手続きがあり、それぞれで条件が異なります。
次の章では、それぞれの特徴と条件を解説します。
個人再生の種類と違い
個人再生の手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
それぞれの違いについては次のとおりです。
| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
| 対象 | アルバイトや自営業者でも条件さえ満たせば利用可能 | 主にサラリーマンなど安定した給与所得がある人 |
| 債務総額 | 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下 | 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下 |
| 再生計画案の認可 | 債権者の頭数の半数以上が反対しないこと、かつ、負債額の1/2を超える債権者が反対しないこと | 債権者の同意は不要 |
| 最低弁済額 | ・最低弁済額 ・清算価値 のうち高い方 | ・最低弁済額 ・清算価値 ・可処分所得の2年分 のうち高い方 |
| メリット | 収入面に関する条件が優しい | 債権者の同意は不要である事 |
| デメリット | 債権者の書面決議で否決される可能性がある | ・小規模個人再生よりも収入面の条件が厳しい ・可処分所得という最低弁済基準が加わるため、弁済額が高額になるケースがある |
2つに共通している点としては
- 将来において継続的、または反復して収入を得る見込みがあること
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
の2点。
それぞれの細かい条件を確認していきましょう。
小規模個人再生の条件
小規模個人再生は、個人再生手続の一種で「住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下で将来にわたり継続的に反復する収入が得られる可能性がある」人が利用できる制度です。
つまり、サラリーマンのように安定した収入がなくても、継続して収入が得られている方は利用できる可能性があるということ。
小規模個人再生の具体的な要件としては次のとおりです。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
- 債権者の半数以上が反対しないこと、かつ、負債額の1/2を超える債権者が反対しないこと
給与所得者等再生の条件
給与所得者等再生も個人再生手続の一種で「住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下で将来にわたり継続的に反復する”安定した収入”が得られる人」が利用できる制度です。
つまり、会社員や公務員など、毎月安定した収入を得ている必要があります。
給与所得者等再生の具体的な要件としては次のとおりです。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
- 給与またはこれに類する安定的な収入を得る見込みがあり、変動の幅が小さいこと
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
- 過去7年以内に給与所得等再生や自己破産、ハードシップ免責をしたことがないこと
大きな違いとしては「給与またはこれに類する安定的な収入を得る見込みがあり、変動の幅が小さいこと」 という条件が加わることです。
変動の幅が小さいというのは、過去2年間の収入に20%以上の変動がないことが基準となります。
一方で、小規模個人再生と違い、債権者の同意を得る必要がない点も特徴です。
- 個人再生の再生計画認可後に予期せぬ事情で返済が困難になった場合、返済金額の4分の3以上の返済を行っていたときは、残りの借金の支払義務を免除してもらえる制度のこと。
- 人生何が起こるか分かりません。病気や怪我、失業、災害など、自分の責任ではない事情で収入が途絶え、計画通りに返済を続けられなくなる可能性もあります。
- そのような場合でも、生活再建の道を閉ざさないために、ハードシップ免責という制度が設けられているのです。
個人再生ができない場合はどんな時?
個人再生や給与所得者等再生といった個人再生手続きをするにはいくつか条件があることは理解できたと思います。
では、個人再生ができない場合というのは具体的にどんな時でしょうか。
主なケースは以下のとおりです。
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている時
- 返済困難な状況にない
- 安定した収入がない
- 高額な財産を所有している
- 個人再生をしても返済の見込みがない
- 個人再生の直前に特定の債権者に対する借金だけ個人再生しようとした
- 債権者から不同意があった
- 個人再生の手続き費用を用意できない
- 借金総額が100万円未満
上記以外にも、個人再生ができないケースはいくつかあります。
個人再生を検討している方は、弁護士などの専門家に相談し、自分の状況で利用できるかどうかを確認するのがおすすめです。
個人再生と他の債務整理方法との違い
借金問題を抱えている方が利用できる債務整理方法には、個人再生の他に、任意整理、自己破産などがあります。
それぞれの手続きには特徴があり、どの方法が適切かは、借金の状況や収入、財産などによって異なります。
ここでは、個人再生と他の債務整理方法との違いを詳しく見ていきましょう。
個人再生と任意整理の違い
任意整理とは、債務者の利息をカットしたり元金を減額するための手段。
厳密に言えば、弁護士や司法書士に依頼して、債権者(お金を貸している業者)に対して「債務(借金)を分割払いにする和解交渉」をしてもらうことを指します。
任意整理をすると、毎月支払っている利息をカットできるため「残りの元金」を分割払いするだけでよくなります。
個人再生との主な違いとしては次のとおりです。
| 個人再生 | 任意整理 | |
| 借金の減額 | 法律で定められた割合で減額 | 将来の利息をカット |
| 対象となる借金 | 原則として全ての借金 | 任意で選択可能 |
| 返済期間 | 原則3年 | 3~5年程度(債権者と交渉) |
| 住宅 | 保持できる | 保持できる |
| 信用情報 | 傷がつく | 傷がつく |
| メリット | 借金を大幅に減額できる | 手続きが比較的簡単 |
| デメリット | 手続きが複雑で費用がかかる | 減額幅が小さい |
最も大きな違いとして借金の減額幅でしょう。
任意整理は将来の利息をカット(元本は減らない)する手続きなので減額幅としては小さいです。その分、費用や手間も少なくて済みます。
一方、個人再生は裁判所を介した複雑な手続きが必要になりますが、借金を大幅に減らすことができます。
個人再生と自己破産の違い
次に個人再生と自己破産の違いについてです。
自己破産も債務整理の一種で、養育費や税金などの非免責債権を除いて、全ての借金をゼロにする手続きのこと。
自己破産の手続きを行うと、裁判所を通じて、借金の返済義務を免除してもらうことができます。
個人再生との主な違いとしては次のとおりです。
| 個人再生 | 自己破産 | |
| 手続き | 裁判所を通して行う | 裁判所を通して行う |
| 借金の減額 | 法律で定められた割合で減額 | 全ての借金が免除 |
| 返済期間 | 原則3年 (場合によっては最長5年) | 返済義務なし |
| 住宅 | 住宅ローン特則を利用すれば自宅を残せる可能性がある | 住宅を含む財産が処分される可能性が高い |
| 信用情報 | 一定期間、信用取引ができない | 一定期間、信用取引ができない |
| メリット | 借金を大幅に減額でき、住宅を残せる可能性がある | 借金の返済義務から解放される |
| デメリット | 手続きが複雑で費用がかかる | 住宅や財産を失う可能性がある |
個人再生は、借金を大幅に減額して返済していく手続きです。
一方、自己破産は、全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きとなります。
個人再生のメリット
個人再生のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 借金を5分の1〜10分の1に減額できる
- 住宅を残しつつ借金を減額できる
- ローンの支払が終わっている場合は車も残せる
個人再生の大きなメリットの一つに、借金を大幅に減額できるという点があります。
個人再生は次の3つの基準を比較して、最も高い金額で最低弁済額として個人再生の手続終了後に支払う借金の総額を決めます。
| 最低弁済額 | ・負債額が100万円未満の場合:負債額全額 ・負債額が100万円以上500万円以下の場合:100万円 ・負債額が500万円超1500万円以下の場合:負債額の5分の1 ・負債額が1500万円超3000万円以下の場合:300万円 ・負債額が3000万円超5000万円以下の場合:負債額の10分の1 |
| 清算価値 | 自己破産をした際に、法律で認められた範囲内で、最低限の生活に必要な財産以外の財産を処分した場合に得られるであろう価値のこと。 |
| 可処分所得基準(給与所得者等再生の場合のみ) | 可処分所得の2年分 |
小規模個人再生の場合は「最低弁済額」と「清算価値」を比較して、高い方の金額で再生計画案を作成。
給与所得者等再生の場合は、可処分所得基準を加えた3つの中で高い方の金額で再生計画案を作成します。
具体的には以下のような例になります。
借金総額が1,000万円清算価値が100万円の人が小規模個人再生をした場合
- 最低弁済額は200万円、清算価値は100万円なので、200万円を支払うことになる。
このように、個人再生では、借金を大幅に減額できる可能性があります。
住宅を残しつつ減額できる
住宅ローンを抱えている人でも、個人再生を利用すれば、住宅を手放さずに借金整理ができる可能性があります。
「住宅ローン特則」と呼ばれる制度を利用することで、住宅ローン以外の借金を減額し、住宅ローンを支払いながら、その他の借金を返済していくことができるからです。
例えば、住宅ローンが2,000万円、その他の借金が1,000万円ある人が個人再生をした場合、住宅ローンはそのまま返済を続けながら、その他の借金を減額して返済していくことができるのです。
自己破産の場合は、時価20万円以上の財産は基本的にすべて処分されてしまうため、住宅もなくなってしまいます。
そのため、マイホームを残しつつ債務整理を進められる点は個人再生の大きなメリットと言えるでしょう。
ローンの支払が終わっている場合は車も残せる
個人再生では、住宅だけでなくローンを完済している車などの財産も残せる場合があります。
自己破産とは異なり、全ての財産を処分する必要はありません。
そのため、ローンを完済した車は自分の所有物なので、個人再生手続き後もそのまま保有できます。
ただし、ローンが残っている車は所有権がローン会社にあるため、一時的に引き上げられる可能性がある点は注意が必要です。
個人再生のデメリット
個人再生にもデメリットは存在します。
具体的なデメリットとしては次のとおりです。
- クレジットカードやローンが、今後約5~7年間できなくなる(ブラックリストに載る)
- 官報に掲載される
- 定期的な収入の見込みがないと利用できない
- 保証人に迷惑がかかる
個人再生の手続きを始める前に、これらのデメリットをよく理解しておくことが重要ですよ。
クレジットカードやローンが、今後約5~7年間できなくなる(ブラックリストに載る)
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
これは、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態で、クレジットカード会社や銀行などが、お金を貸すかどうかを判断する時に利用する情報です。
信用情報は、クレジットカードやローンの審査に使われるため、事故情報が載っていると審査に通らなくなります。
具体的には、新規のクレジットカードを作ることや、住宅ローン、自動車ローンを組むことが難しくなるでしょう。
このように、個人再生は信用情報に傷をつけるというデメリットがある点は注意が必要です。
官報に掲載される
個人再生をすると、官報に氏名や住所などが掲載されます。
官報は、国が発行する機関紙で、法律や条例、国の予算、決算などの公的な情報が掲載されています。
官報は、誰でも見ることができますが、一般的に官報を見る人は多くありません。
そのため、官報に掲載されたことで、日常生活に大きな支障が出ることは少ないと考えられます。
定期的な収入の見込みがないと利用できない
定期的な収入の見込みがないと、個人再生を利用できません。
個人再生では、裁判所が認可した再生計画に基づいて、3年〜5年かけて借金を返済していく必要があります。そのため、安定した収入がなければ、計画的に返済を続けることが難しいと判断されてしまうからです。
保証人に迷惑がかかる
借金に連帯保証人や保証人がついている場合、個人再生をすると連帯保証人や保証人が代わりに返済義務を負うことになります。
個人再生した本人は借金が減額されますが、保証人に対しては減額されないため、一括返済が求められることが多いです。
例えば、借金が400万円あり、個人再生によって100万円に減額されたとします。
この場合、残りの300万円は債権者から連帯保証人に一括請求される可能性があるということです。
そのため、保証人がいる場合は保証人と話し合いをして、しっかりと理解を得ることが重要です。
個人再生手続きの手順
個人再生の手続きは、複雑で専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
個人再生の大まかな流れとしては次のとおり。
- 弁護士に相談
まずは、弁護士に相談し、自己破産が可能かどうか、どのような手続きが必要かなどを確認します。2 - 債務整理の依頼
弁護士に個人再生の手続きを依頼します。委任契約を結び、費用や手続きの流れについて説明を受けます。 - 受任通知の発送
弁護士が、債権者に対して、受任通知を発送します。受任通知が債権者に到達すると、債権者からの請求・督促が止まります。 - 債権調査
弁護士が、債権者に対して、債務内容を調査・確認します。債権者から取引履歴等を取り寄せ、現在の負債額などを調査・確認。 - 申立書類の準備
- 申立
弁護士が裁判所に対して個人再生手続開始の申立てをします。 - 約一ヶ月後、個人再生手続きを開始
裁判所は、申し立ての内容を審査し、個人再生手続きを開始するかどうかを決定します。通常、申し立てから約1ヶ月後に決定。また、再生手続開始決定は官報に載ります。 - 賃金業者へ債権届出を送付
申立書を元に、まずは債権者に借金の額があっているかを確認。 - 債権認否一覧表を提出
- 弁護士が再生計画案を提出
弁護士が、債務者と相談しながら作成した再生計画案を裁判所に提出します。再生計画案には、返済期間、返済方法、返済額などが記載されます。 - 書面による決議
- 裁判所から再生計画認可決定
裁判所が再生計画案を認可すると、債務者は、その計画に従って借金を返済していくことになります。 - 再生計画に沿って返済
まとめ
個人再生は、借金を抱えて生活が苦しくなった人が、裁判所を通して借金を大幅に減額してもらい、残りの借金を3~5年かけて返済していく手続きです。
しかし、メリットだけでなく、デメリットも存在します。
そのため、自己破産を検討する際は、メリットとデメリットをよく理解し、慎重に判断することが重要です。
ご自身の状況をしっかりと把握し、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
もし、借金問題でお悩みでしたら、一人で悩まずに、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
個人再生に関するよくある質問
 個人再生の成功率はどれくらいですか?
個人再生の成功率はどれくらいですか?
日弁連が発表している「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、個人再生事件のうち認可決定で終結した割合は91.70%で、個人再生の成功率は90%を超えていることが分かります。