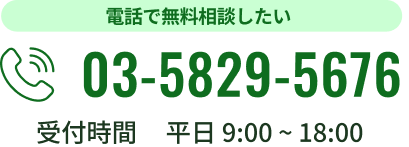自己破産とは ?メリットとデメリットから相談するとどう影響するのか解説

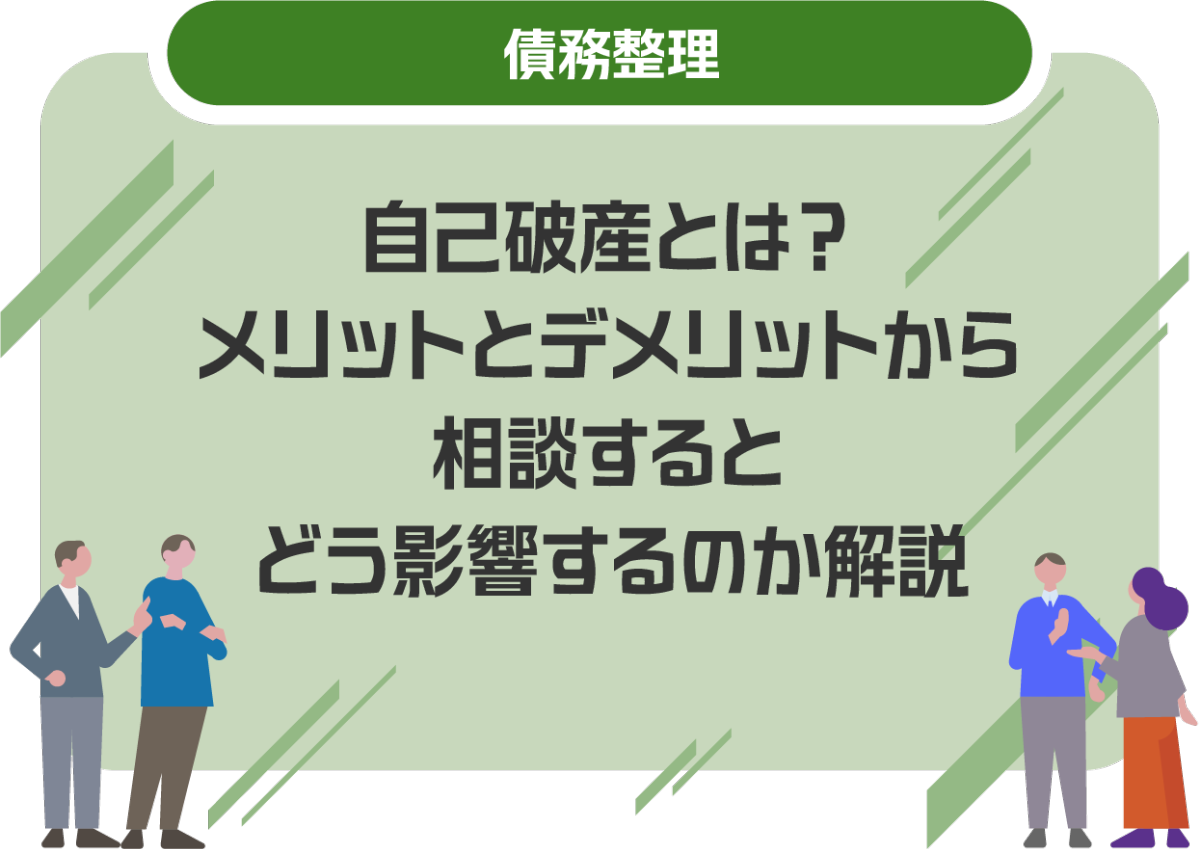
ただ、自己破産と債務整理はどんな違いがあるのか、今後の生活にデメリットは生じるのかなど不安や疑問を多く抱えている方も少なくありません。
この記事では、自己破産に関する情報をわかりやすく解説します。
- 自己破産は借金問題を抱えている人が経済的にやり直すための法的な手続き
- 自己破産のデメリットは金融ブラック・物品の回収・連帯保証人への影響の3点
- 自己破産の費用目安は費用相場は30万〜80万円程で手続の種類によって異なる
- 自己破産はほぼ弁護士に丸投げでOK!
自己破産とは債務整理の1つの手段である
自己破産とは、借金問題を抱えている人が経済的にやり直すための法的な手続きです。
「破産」と聞くと、マイナスのイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、自己破産は借金で苦しむ人を救済するための制度です。
自己破産をすると、養育費や税金などの非免責債権を除いて、全ての借金をゼロにする事が可能。
自己破産の手続きを行うと、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらうことができます。
つまり、自己破産は「もう、どう頑張っても借金を返すことができない!」という支払不能な状態に有効な手段と言えるでしょう。
自己破産と債務整理の違い
借金で悩んでいる時に「債務整理」と「自己破産」という言葉を聞くけれど、何が違うのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
簡単に言うと「債務整理」は借金問題を解決するための方法全体のことで「自己破産」はその中の一つです。
債務整理 は、借金で困っている人が法律を使って借金を減らしたり、返済方法を変えたりして生活を立て直すための手続きで、大きく分けて以下の4つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 特定調停
- 自己破産
債務整理というカテゴリーの中の1つが自己破産という理解で問題ありません。
自己破産ができる条件は?
自己破産は借金でどうしようもなくなった時に助けてもらえる制度であることは確かです。
しかし、誰でもできるわけではありません。
ここでは、自己破産を行うために必要な3つの条件について解説します。
- 債務が「支払不能」状態であること
- 債務が「免責不許可事由」にあたらないこと
- 債務が「非免責債権」ではないこと
債務が「支払不能」状態であること
自己破産をするための最も重要な条件は「支払い不能」状態であることです。
簡単に言うと「もう、どう頑張っても借金を返すことができない」 という状態のこと。
「支払い不能」かどうかは、裁判所があなたの収入や財産、借金の状況などを総合的に見て判断します。
「借金がいくら以上あれば自己破産できるの?」と思う方もいるかもしれませんが、 借金の額は、実はあまり関係ありません。
借金が少ない場合も、収入や財産がほとんどなく、借金を返済できる見込みがないと判断されれば自己破産できる可能性はあります。
逆に、借金がたくさんある場合も、安定した収入があって、家や車などの財産を売れば借金を返済できる場合は自己破産は難しいでしょう。
つまり「支払い不能」かどうかは借金の額ではなく、あなたの今の経済状況と借金を返済できる見込みがあるかどうかで判断される ということです。
債務が「免責不許可事由」にあたらないこと
自己破産をすると、借金のほとんどはゼロにしてもらえます。
中には、自己破産をしても帳消しにできない借金や免責されないケースがあります。
これを「免責不許可事由」と言います。
ちょっと難しい言葉ですが、簡単に言うと「こんなことをしていたら、自己破産は認めませんよ」というルールのことです。
具体的な免責不許可事由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 返済する気がないのに借金をする行為
- 債権者を侵害する目的で自らの財産を減少させたり隠す行為
- 裁判所に対して財産を隠したり、嘘の申告をする行為
- 特定の債権者にだけ返済する行為(偏頗弁済)
- ギャンブルや浪費で作った借金
- 前回の免責許可決定の日から、7年以内に免責許可を申立てる行為
これらの借金や行動は「免責不許可事由」にあたるので、自己破産をしても借金が免責にならない可能性が高いです。
ただし、これらのことをしたからといって、 必ずしも自己破産が認められないわけではありません。
そのため、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
債務が「非免責債権」ではないこと
自己破産をしても、 免責にできない借金 があります。
これを「非免責債権」と言います。
非免責債権としては、以下のようなものが挙げられます。
- 税金所得税(消費税、贈与税、住民税、固定資産税など)
- 公共料金(水道料金)
- 社会保険料
- 損害賠償金
- 養育費
- 罰金
- 慰謝料
- 従業員への給与(※個人事業主の場合)
自己破産で税金が帳消しになってしまったら、真面目に税金を払っている人たちが不公平に感じますよね。
自己破産は、借金で困っている人を助けるための制度ですが、社会全体のバランスも考えないといけないのです。
自己破産するとどうなるの?
自己破産をすると3つのメリットと4つのデメリットが生じます。
今の自分の場合、メリットとデメリットどちらの方が大きいのかを確認していきましょう。
- 借金の支払い義務が免除される
- 債権者からの取立てを止められる
- 財産をすべて失うわけではない
- クレジットカードやローンの利用が約5~10年間、契約できなくなる
- 高価な財産を処分される
- 官報に掲載される
- 一部の職業に就けなくなる
自己破産のメリット
自己破産のメリットは以下のとおり。
- 借金の支払い義務が免除される
- 債権者からの取立てを止められる
- 財産をすべて失うわけではない
自己破産のメリットは「生活に必要な最低限の財産を残しながらすべての借金の支払い義務が免除されること」です。
自己破産をすることで、消費者金融からの借り入れや、クレジットカードの負債、カードのキャッシングなど、すべての借金の支払い義務が免除されます。
また、すべての借金が免除されたとしても、洗濯機や冷蔵庫などの生活に必要な家財道具まで処分されてしまうと、その後の生活が成り立たなくなってしまいますよね。
そのため、
- 生活必需品
- 20万円以下の預貯金
- 現金99万円まで
- ローンのない市場価値22万円未満の車
など、生活に必要な財産は、手元に残すことができます。
自己破産のデメリット
「借金を帳消しにできる」という観点では大きなメリットがある自己破産ですが、デメリットも存在します。
主なデメリットは以下の4点です。
- クレジットカードやローンが、今後約5~10年間、契約できなくなる
- 高価な財産を処分される
- 官報に掲載される
- 一部の職業に就けなくなる
それぞれ、詳しく解説します。
クレジットカードやローンが今後約5~7年間、契約できなくなる
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
これは、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態で、クレジットカード会社や銀行などが、お金を貸すかどうかを判断する時に利用する情報です。
信用情報は、クレジットカードやローンの審査に使われるため、事故情報が載っていると審査に通らなくなります。
具体的には、新規のクレジットカードを作ることや、住宅ローン、自動車ローンを組むことが難しくなるでしょう。
このように、自己破産は信用情報に傷をつけるというデメリットがある点は注意が必要です。
高価な財産を処分される
自己破産をすると、一定以上の価値がある財産は処分され、債権者に分配されます。
これは、債権者の損失を少しでも補填するためです。
具体的には、20万円以上の価値があるものが処分の対象となります。
例えば、高価な宝石やブランド品、高級車、持ち家などが挙げられます。
ただし、生活に必要な家財道具や仕事道具は、原則として処分されません。
官報に掲載される
自己破産をすると、官報に氏名や住所などが掲載されます。
官報は、国が発行する機関紙で、法律や条例、国の予算、決算などの公的な情報が掲載されています。
官報は、誰でも見ることができますが、一般的に官報を見る人は多くありません。
そのため、官報に掲載されたことで、日常生活に大きな支障が出ることは少ないと考えられます。
一部の職業に就けなくなる
自己破産をすると、一定期間、一部の職業に就けなくなることがあります。
具体的には
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 不動産鑑定士
- 警備員
- 生命保険募集人
などが挙げられます。
ただし、制限されるのは自己破産の手続き中のみです。
具体的にいえば、裁判所への申立後から免責決定(借金が免除になる決定)が確定するまでの期間となっています。
自己破産の申立内容によっても期間は多少前後しますが、一般的には3ヶ月〜半年程度で制限は解除されるでしょう。
連帯保証人・保証人も自己破産をすることになる
借金に連帯保証人や保証人がついている場合、自己破産をすると連帯保証人や保証人が代わりに返済義務を負うことになります。
自己破産した本人は債務を免除されますが、その負担が保証人に移るため、保証人には一括返済が求められることが多いです。
もし、該当する借金が少額であれば、連帯保証人や保証人が支払いを引き受けられる可能性もあるでしょう。しかし、保証人にとって、その負担が大きければ結果として保証人も自己破産を検討せざるを得ない状況になることがあります。
そのため、保証人がいる場合は、保証人と話し合いをして、しっかりと理解を得ることが重要です。
自己破産はしないほうが良い?したほうが良い人としないほうが良い人の特徴
自己破産は、借金問題を抱えている人にとって、一つの解決策となる場合があります。
しかし、必ずしもすべての人にとって最良の選択肢とは限りません。
自己破産をした方が良いと言える人の特徴としては、以下のような点が挙げられます。
自己破産をしたほうが良い人の特徴
- あまりにも多額の借金があり、返済の目処が立たない人
- 財産が少ない人
- 将来の収入の見込みがない人
まとめると、あまりにも多額の借金があるが、高価な財産を所持していない上、返済目処が立たない人は自己破産したほうが良いでしょう。
自己破産をしないほうがよい人の特徴
逆に自己破産をしないほうが良い人の特徴としては、以下のような点が挙げられます。
- 家や車などの財産を手放したくない人
- 他の手段を使えば返済できる人
- 家族に知られたくない人
- 資格制限のある職業に就いている、または将来就きたいと考えている
自己破産は、借金問題を解決するための有効な手段の一つです。
しかし、上記のような特徴に当てはまる人は、他の債務整理方法を検討するか専門家に相談することをおすすめします。
自己破産の費用相場はいくら?
ただ、自己破産も無料でできるわけではありません。自己破産の費用相場は30万〜80万円程です。
費用の内訳は、大きく分けて
- 裁判所費用
- 弁護士費用
の2種類になります。
また、自己破産には、主に3つの手続きがあり、それぞれで裁判所費用と弁護士費用が異なります。
| 手続きの種類 | 裁判所費用 | 弁護士費用 | 総額 |
| 同時廃止事件 債務者の財産が少なく、かつ免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がない場合に選択される手続きです。 | 約1~3万円 | 約50万円 | 約50万円 |
| 管財事件 債務者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合に選択される手続きです。 | 約50万円 | 約50~80万円 | 約100~130万円 |
| 少額管財事件 債務者に一定の財産があるものの、管財事件を行うほどではない場合に選択される手続きです。 | 約20万円 | 約50~60万円 | 約70~80万円 |
どの手続きになるかは、借金の状況や財産の有無などによって裁判所が判断します。
費用面で不安な場合は、弁護士・司法書士に相談し、自分に合った方法を見つけるようにしましょう。
山本綜合法律事務所の自己破産費用
当事務所では、次の費用を目安に引き受けさせていただいております。
- 自己破産の費用 税込み500,000円 〜
- 管財人に掛かる費用 税込み500,000円
無料相談も利用可能ですので、まずは「自己破産をしたほうが将来的によいのかどうか」など気になることを気兼ねなくご質問ください。
借金問題に精通した当事務所の弁護士が対応いたします。
自己破産の流れ
自己破産の主な流れは以下のとおり。申し立てから解決までの期間目安は6~8か月です。
ここでは、管財事件型 と 同時廃止型 の2つの手続きに分けて解説します。
管財事件型
管財事件とは、ある程度の財産を保有している場合に行われる手続きです。家や車、預貯金など、換価できる財産がある場合、裁判所が選任した破産管財人がそれらを売却し、債権者に配当します。
1.弁護士に相談
まずは、弁護士に相談し、自己破産が可能かどうか、どのような手続きが必要かなどを確認します。
2.債務整理の依頼
弁護士に自己破産の手続きを依頼します。
委任契約を結び、費用や手続きの流れについて説明を受けます。
3.受任通知の発送
弁護士が、債権者に対して、受任通知を発送します。
受任通知が債権者に到達すると、債権者からの請求・督促が止まります。
4.債権調査
弁護士が、債権者に対して、債務内容を調査・確認します。
債権者から取引履歴等を取り寄せ、現在の負債額などを調査・確認。
5.申立
弁護士が裁判所に対して破産手続開始し、免責許可の申立てをします。
6.破産管財人の選任・面談
申立後、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人との面談があり、事情の説明や財産等の引継ぎを行います。
7.破産手続開始決定
裁判所は、借金等を支払う資力がないと判断すると、破産手続開始決定を出します。
以後、破産管財人による調査が開始。
8.債権者集会
裁判所において、債務者、弁護士、破産管財人、債権者が集まり、破産管財人から財産状況等の報告や免責に関する意見が出されます。
9.免責審尋
裁判官による免責審尋が行われ、自己破産を認めるかどうかが判断されます。
10.免責許可決定
裁判所が免責を認めると、免責許可決定が出され、官報に公告されます。
同時廃止型の場合
同時廃止事件とは、所有している財産がほとんどなく、債権者に配当できる見込みがない場合に認められる手続きです。裁判所が破産宣告と同時に破産手続きを終了させるため、手続き期間が短く、費用も比較的安く済むのが特徴です。
1.弁護士・司法書士に相談~申立
管財事件型と同様です。
2.破産審尋
申立てをする裁判所の方針や案件内容によって異なりますが、申立後、破産審尋期日(裁判所に出頭する日)が指定され、裁判官から破産に至った経緯等の質問を受けることがあります。
3.破産手続開始決定
裁判所は、借金等を支払う資力がないと判断すると、破産手続を開始する旨の決定と、同時に破産手続が終了する旨の決定を出します。
4.免責審尋
破産手続終了後、裁判所が免責の可否を判断する上で、免責審尋期日が指定され、裁判官から免責判断に必要な質問を受けることがあります。
5.免責許可決定
管財事件型と同様です。
自己破産にかかる期間は6〜8ヶ月程度
あくまで目安ではありますが、自己破産にかかる期間は6〜8ヶ月程度であることが多いです。
特に、複雑ではなく債権者も多くない案件の場合、半年程度で自己破産が完了します。
また、長期戦で精神的負荷が大きくなりすぎることがないよう、当事務所の弁護士が徹底的にフォローいたします。
まとめ
自己破産は、借金問題で悩んでいる人にとって、人生をやり直すための有効な手段の一つです。
しかし、自己破産にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。
そのため、自己破産を検討する際は、メリットとデメリットをよく理解し、慎重に判断することが重要。
ご自身の状況をしっかりと把握し、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
もし、借金問題でお悩みでしたら、一人で悩まずに、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
自己破産に関するよくある質問
自己破産すると携帯電話はどうなりますか?
以下の条件を満たす場合は自己破産後も携帯電話を使うことができます。
- 分割払いがすべて支払い済み
- 未払いの利用料金がない
- 携帯電話本体が20万円以下
自己破産すると家族はどうなりますか?
結論として、家族に負担を全くかけずに自己破産するのは難しいでしょう。
具体的には以下のような影響があると考えられます。
- 持ち家や車がなくなる
- 現金がなくなる(手持ちの財産総額が99万円を超える場合)
- 家族が保証人の場合は返済義務が生じる
- 20万円以上の解約返戻金のある保険は全て解約される
- 自己破産する本人名義で作った家族カードも使えなくなる
自己破産したら何を失いますか?
自己破産をしたからといって、何もかも失うわけではありません。
20万円以上の価値があるものや資産として認定されるものは失いますが
- 生活必需品
- 20万円以下の預貯金
- 現金99万円まで
など、生活に必要な財産は、手元に残すことができます。
自己破産すると年金はどうなりますか?
自己破産をしても、原則として国民年金や厚生年金などの公的年金の受給には影響がありません。
公的年金が「差押禁止財産」に分類されているためで、受給権は法律によって保護されているからです。