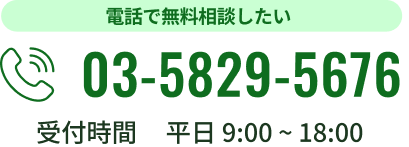時効の援用の成功率は約9割って本当?成功率を高めて失敗を避ける方法を説明
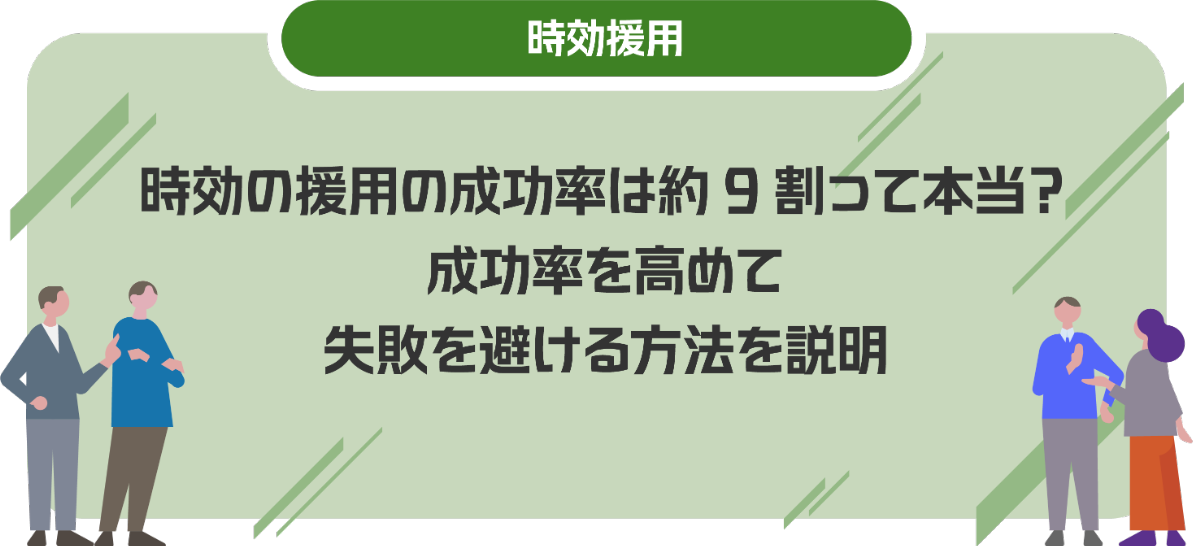
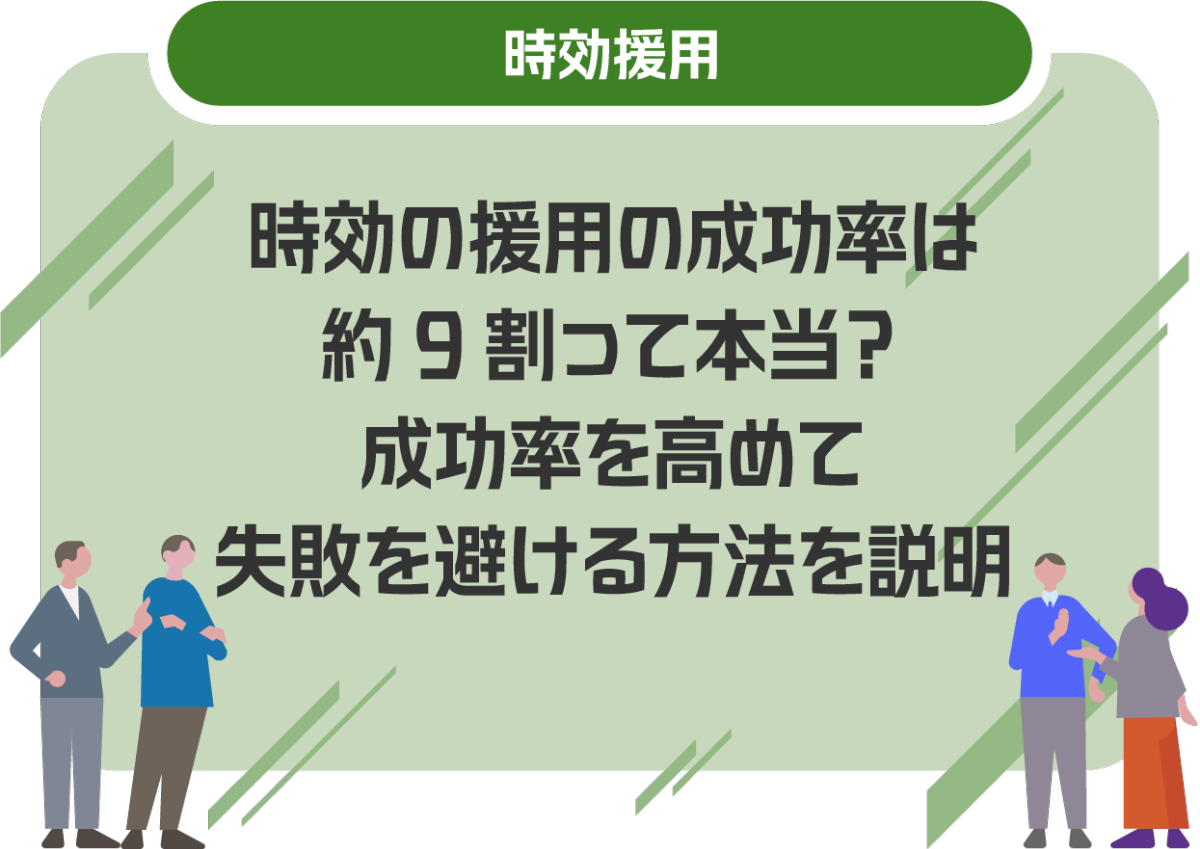
「でも成功する確率って高いのかな?それとも低いんだろうか。」
と疑問に思っている方が今記事を読んでいるのではないでしょうか。たしかに、どれくらいの確率で時効の援用に成功するか気になりますよね。
この記事では、以下の3点を中心にあなたの疑問を解消します。
- 時効の援用の成功率
- 時効の援用に失敗してしまう原因
- 時効の援用の成功確率を上げるための方法
時効の援用の成功率は約9割と高め
時効の援用の成功率は約9割と言われています。思ったよりも高いなと思った方も多いのではないでしょうか。
時効の援用は「借金の消滅時効が完成していて、正しい形式で時効援用通知書を送付」すれば理論上「間違いなく成功」します。時効の援用は法的に認められている「債務者(借りる側)の権利」ですからね。
そして、時効が完成していないと判断される場合はそもそも「援用をしよう」とアクションを起こしません。
この2点が「約9割」という高い成功率になっている理由です。
残り1割はなぜ失敗してしまう?
では、なぜ残りの1割は失敗してしまうのでしょうか。
もちろん、時効援用通知書に不備があったり、債権者(お金の貸し手側)の情報が不足していて、債権の特定ができなかった場合もあります。
しかし、時効の援用に失敗してしまう理由の殆どは「借金の消滅時効が完成していると思ったら要件を満たしていなかったこと」に起因します。
時効の援用の失敗原因の多くは「消滅時効が実は完成していなかった」こと
では、時効の援用の主な失敗原因である「消滅時効が未完成だったから」というケースはどのように生じてしまうのでしょうか。
主な原因は以下の3つです。
- 相手から裁判を起こされて「時効の更新」がされていた
- 途中で返済をしていて「最終支払日」を勘違いしていた
- 督促状を見て連絡をしてしまい「債務の承認」をしてしまった
それぞれ、なぜ失敗の原因になってしまうのか、どうすれば良いのかの2点を中心に解説します。
関連記事:時効の援用に失敗してしまうとどうなる?失敗例やその後にとるべき対応を解説
相手から裁判を起こされて「時効の更新」がされていた
債権者(貸し手側)から裁判を起こされていると「時効が更新」されます。(時効の更新)
裁判を起こされてしまうと「裁判を起こす=債務者(借り手)側に支払い要求をする意思表示」として捉えられてしまうからです。
裁判をして時効の更新がされると「時効の更新がされた日」から5年もしくは10年待たなければいけなくなります。
そして、債務者(借り手)側が裁判をされていたことに気づかないと「時効が完成していない状態にもかかわらず時効の援用をしてしまう」という事態に繋がります。
ですから、もし裁判所から訴状が届いた場合には捨てたり、無視したりせず「いつ送られてきたのか」を記録しておくようにしましょう。
とはいえ、過去に裁判がされていたかどうか自己判断することは非常に困難です。
成功率を上げたい場合は弁護士等の「専門家」に依頼したほうがトータルで見て「プラス」に働くことが多いです。
途中で返済をしていて「最終支払日」を勘違いしていた
人の記憶とは思っている以上に曖昧なことが多いです。
「最終支払いをしてから5年以上経過したから時効の援用ができる!」と思ったものの、よくよく調べたら3年前に督促状が届いていて、一部支払をしていた。
なんてケースもあります。最終支払日や返済期限に関しては「CICやJICCなどの信用情報機関」に情報開示すれば調べられます。
時効の援用をする際には、必ず信用情報の開示を行い、以下の項目を調べましょう。
- 契約年月日/貸付日契約日→5年(10年)以上経過しているか
- 出金日利用日→5年(10年)以上経過しているか
- 返済状況/異動参考情報
- 入金状況/入金日/最新支払日→5年(10年)以上経過しているか
督促状を見て連絡をしてしまい「債務の承認」をしてしまった
一般的に債務の承認として取られる行動は以下の通り。
ただし、具体的な事例や法律によって適用されるかどうかは変わる可能性があるため、法的な助言を必要とする場合は弁護士をはじめとした専門家に相談してください。
- 債務の返済: 債務を返済する行為は、債務の存在を認めることになるため、債務の承認となります。
- 債務の返済を約束する文書の作成や署名: 債務の存在を認め、返済を約束する書面を作成した場合、これは債務の承認となります。
- 債務の存在を認める声明: 口頭であるか文書であるかに関わらず、債務の存在を認める声明を行うと、これも債務の承認となります。
- 一部返済や利息の支払い: 債務全体を返済するのではなく一部を返済したり、利息を支払ったりする行為も、債務の存在を認めることになります。
- 債務の返済を求める催告に対する応答: 債務の存在と返済の必要性を認め、その催告に応答する行為も債務の承認となる可能性があります。
対処法は「自分でなんとか対応しないこと」です。どの行為が「債務の承認」として取られてしまうかの判断は困難なので、なにかアクションを起こす前に専門家へ相談しましょう。
時効の援用の成功率を上げるなら「プロへの依頼」がベスト
借金の消滅時効の完成を自分で判断するのは手間もかかりますし、不確実性が伴ってしまいます。もし、時効の援用に失敗してしまうと次のチャンスは早くて5年後。
その間、少なからず精神的負荷を感じ続けることになってしまいます。さらに、時効の援用をするためには以下も必要になります。
- 時効援用通知書の作成
- 内容証明での送付
- 通知書の送付後の結果確認
これらのリスク・労力を加味すると、費用を払ってでもプロへ依頼してしまうのが時間効率が良いと言えます。
何年も悩まされてきた借金が3万円程度で解決できる可能性が高いわけですからね。
時効の援用のプロ(弁護士)に依頼をするメリット
とはいえ、なんのメリット提示もなしに「専門家に依頼しよう!」と言われても、なかなか受け入れがたいですよね。
そこで、時効の援用をプロ(弁護士)に依頼するメリットは何があるかも具体的に紹介します。
主なメリットは以下の3点。
- 成功率を上げられる
- 失敗して時効が伸びる、損害遅延金を請求されるリスクを最小限にできる
- 時間も手間もかからない
何より「成功率を上げ、さらなる経済負担増を回避できる点」が最大のメリットといえます。
もし、上記のメリットに魅力を感じているのであれば、次に説明する弁護士への依頼費用をチェックし「メリットの方に魅力を感じるか、費用の高さに意識がいくのか」を判断してみてください。
もしあなたの感じ方が前者に近いのであれば、依頼したほうが納得いく結果が得られる可能性が高いです。また、後者の「マイナス要因」のほうが大きく感じる場合は「なんとか自力で行う」のも一つの手です。
関連記事:時効の援用のやり方は?手続きの流れと時効援用通知書の書き方を解説
関連記事:時効援用通知書を自分で書く場合の流れ
時効の援用を弁護士に依頼した場合費用はいくら?
一般的には、時効の援用の依頼にかかる費用の相場は「3万円から5万円」です。
この費用には以下の作業が内包されていると考えてください。
- 時効が完成しているかどうかの調査
- 時効援用通知書の作成
- 内容証明郵便での送付
- 相手方への確認 など
ただし、弁護士事務所によっては依頼の内容やケースの複雑さにより「費用が増えてしまうこと」もあります。
しかし、当事務所では、全てのお客様に対して一律「28,000円」で時効の援用のサービスを提供しています。
追加費用をいただくことはありません。
まずは、時効が完成しているかどうか「無料相談」で伺わせていただければ、あなたの力になれるよう当事務所の経験・知見のある弁護士が対応いたします。
どうしても自分で時効の援用をしたい場合、失敗を回避する方法はある?
「自分で出来る可能性があるのなら自分でやりたい!」と思う気持ちは非常によくわかります。費用が浮けばその分他のことにお金を使えますからね。
この章では「自分で時効の援用をする場合」にできるだけ失敗を回避する方法を紹介します。ただし、一定の失敗リスクは伴いますので、その点を許容できる人向けの内容です。
信用情報機関への情報開示請求をしっかりとする
まずは、「信用情報機関(CICとJICC)」に情報開示請求をしましょう。開示請求にかかる費用は500円〜1500円です。
既出の内容になりますが、情報開示請求をして以下項目を入念にチェックしましょう。1項目クリアしているからといって他の項目チェックを怠ってはいけません。
- 契約年月日/貸付日契約日→5年(10年)以上経過しているか
- 出金日利用日→5年(10年)以上経過しているか
- 返済状況/異動参考情報
- 入金状況/入金日/最新支払日→5年(10年)以上経過しているか
記憶違いがないように口座の振込・引き落とし履歴をチェックする
過去に自分で支払いをしていないかどうかも徹底的に調べましょう。
銀行通帳の履歴を可能な限り取得して、途中で返済をした形跡がないかどうか調べましょう。
信用情報の開示と合わせて行うことで「勘違いによる失敗」のリスクを最小限にできます。
時効援用通知書の記入漏れがないかダブルチェックする
最後は、作成した時効援用通知書に不備がないかダブルチェックをしましょう。
特に以下の項目がしっかりと明記されているか確認することが大切です。
- 送付先を記載されているか
- 時効の援用をする日付を記載されているか
- 債権を特定できる情報を記載されているか
- 消滅時効を援用する旨は記載されているか
- 送り主(自分の情報・実印)を記載されているか
不備がなければ、必ず「内容証明郵便」で送付し、控えも郵便局用と自分用の2部用意しておきましょう。
普通郵便で送ってしまうと「受け取った証明」ができないため、自分が不利になってしまいます。1000円程度費用はかかるものの、必ず「内容証明郵便」を利用してください。
関連記事:時効の援用通知書を自分で書く場合のポイントと注意点をわかりやすく解説
まとめ|時間と労力を考えると時効の援用はプロへの依頼が効率的
この記事の結論は以下の2点です。
- 時効の援用の成功率は約9割と高い
- 時効の援用の成功率を上げるならプロに相談するが吉
なかには、なんとか自分で対応しようと思っている方もいるとは思います。しかし、失敗してしまっては費用を抑えても意味がありません。本末転倒です。
時効の完成の判断や援用手続きはプロに任せたほうが、満足の行く結果が得られます。まずは気軽にLINE相談から始めてみましょう。