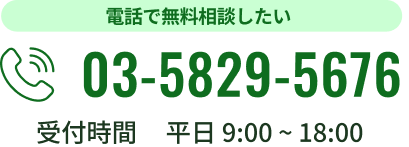借金の消滅時効とは?適用される条件や本当に借金がなくなるのかわかりやすく解説
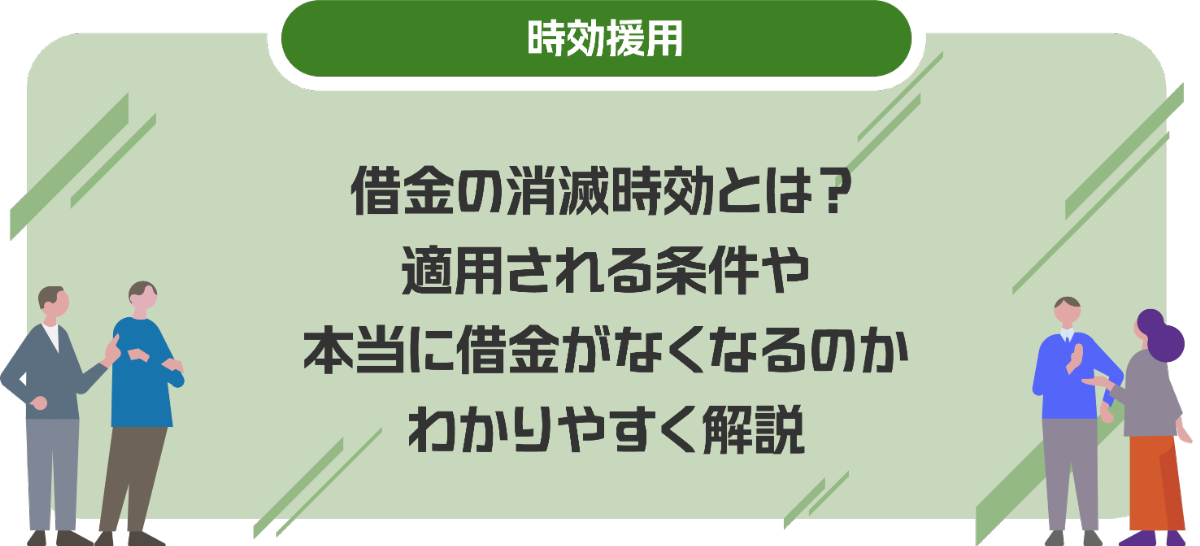
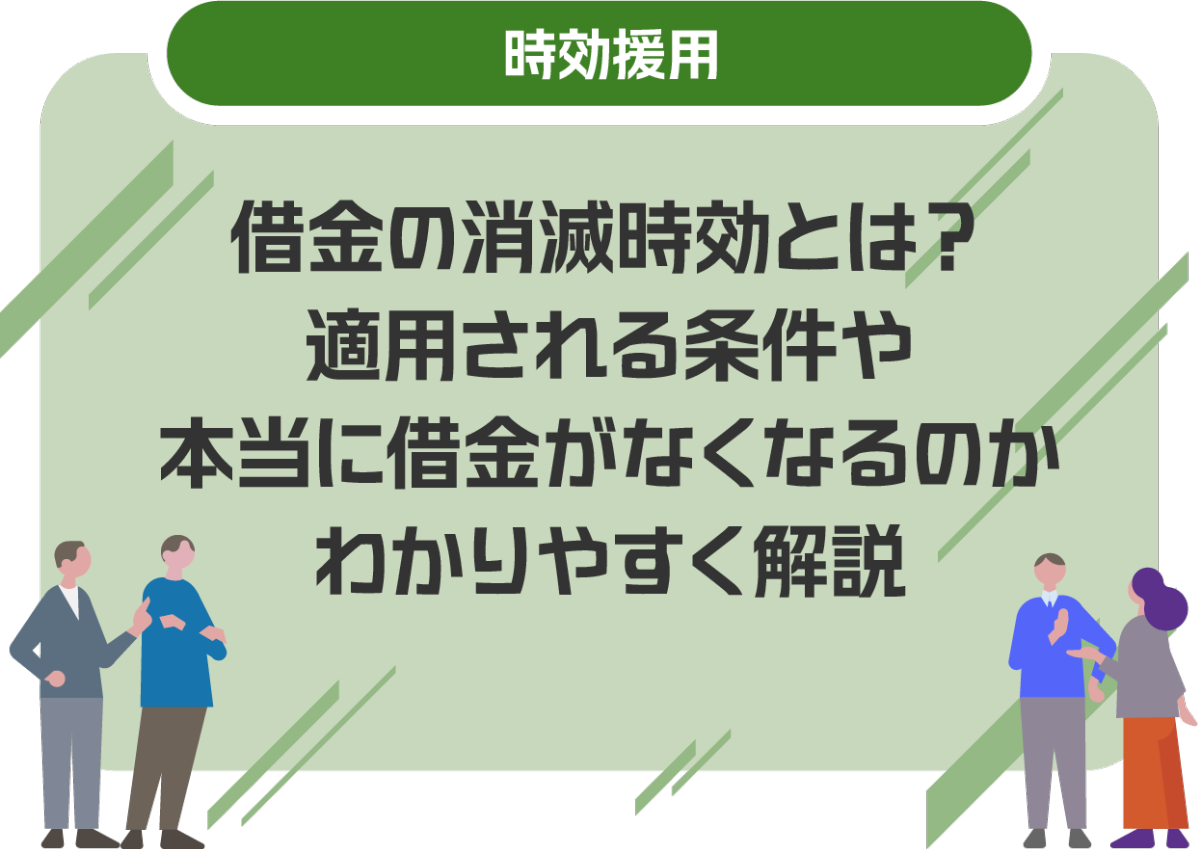
と悩んでいる方はいませんか?
借金には「消滅時効」という名の時効が存在します。
しかし、消滅時効は時間が経てば適用されるわけではありません。
本記事では、借金の消滅時効の定義や適用される条件などを詳しく解説します。
借金を少しでも減らしたい方や、古い借金の返済をいきなり迫られて困っている方は、参考にしてください。
借金の消滅時効とは?
借金の消滅時効とは一定の期間が経過した借金は支払わなくてもよい、という決まりです。
確かに借りたがずっと返済をしておらず、自分自身も借金をしたことを忘れていた、といったケースもゼロではありません。
「何年も前の借金をいきなり返済しろと言われて困った」と悩んでいる方もいるでしょう。
そのため、法律では「お金を貸した側が借りた側に借金を回収する権利」を行使しないまま一定期間が過ぎると、回収する権利を失うと定めています。
つまり、お金を貸した側が一定期間「借金を返してください」と催促して、お金を借りた側が「返します」と約束したり返済したりしないと、借金は消滅するのです。
しかし、ただ時間が経てば無条件に借金が消滅するわけではありません。
以下の項で、借金の消滅時効が適用される条件や法律について詳しく解説していきます。
| 専門用語 | 意味 |
|---|---|
| 時効 | ある出来事から一定期間が経過したことを尊重し、法律的に正当でなくても権利を認めること |
| 債権者 | お金を貸した側 |
| 債務者 | お金を借りた側 |
| 主観的起算点 | 借金の債権者であると知ったとき |
| 客観的起算点 | 借金の債権者になったとき |
令和2年4月1日以降の借金は「改正民法」が適用される
2020年(令和2年)4月1日、消滅時効に関する民法が改正されました。
改正された民法では、「職業別の短期消滅時効の見直し」「時効期間と起算点に関する見直し」などが行われ、消滅時効に関するルールがよりシンプルになったのです。
改正民法で、重要視されるのは「主観的起算点」と「客観的起算点」です。
「主観的起算点」と「客観的起算点」の意味と消滅時間は以下の表の通りとなっています。
なお、改正前の民法にあったような、職業や借金をした目的による時効の差はなくなりました。
また、2つの時効消滅期間のうち早いタイミングの時効期間が適用されます。
ちなみに、改正民法が適用されるのは、2020年4月2日以降に行われた借金です。
| 主観的起算点 | 借金の債権者であると知ったとき | 消滅時効:5年 |
| 客観的起算点 | 借金の債権者になったとき | 消滅時効:10年 |
一例を挙げてみます。
Aさんの父はBさんへ、2020年4月3日に500万円のお金を貸しました。しかし、Aさんの父はAさんにそれを告げることなく亡くなり、財産一式はAさんが相続しています。
そして、2022年にAさんはBさんに父がお金を貸していると知ったのです。
この場合、借金の消滅時効は主観的起算点が適用されるので2027年です。
したがって、AさんはBさん、もしくはBさんの遺産を相続した方に500万円の返済を要求できます。
しかし、Bさん、もしくはBさんの遺産を受け継いだ相続人が所在不明で見つけられなかったり「借金を返す」と明言しなかったりすると、2026年に消滅時効を迎えます。
出典:法務省【消滅時効に関する見直し】
令和2年3月31日以前の借金は「改正前民法」が適用される
令和2年3月31日以前に行った借金は、改正前民法が適用されます。
改正前民法では、職業によって時効が異なりました。
一例をあげると、以下の表の通りです。
| 債権者の職業 | 時効の起点 | 時効の年数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 借金の債権者になったとき | 10年 | 個人間の借金 住宅ローン 奨学金 信用保証協会の求償権 |
| ホテル・レストラン・居酒屋 | 借金の債権者になったとき | 1年 | 家賃・つけの飲食代・ホテル代 |
| 医師、助産師・マッサージ師 | 借金の債権者になったとき | 3年 | 診療報酬 |
| 消費者金融 銀行 | 借金の債権者になったとき | 5年 | フリーローンなど |
一例を挙げてみましょう
居酒屋を営むAさんは、帳簿を整理していた時3年前にツケでBさんに飲食をさせていたことに気が付きました。しかし、ツケの飲食代は1年で時効消滅するため、気付いた時点でBさんはすでに回収する権利を失っていたのです。
DさんはEさんから、2018年に30万の借金をしました。しかし、Eさんがその後遠くに引っ越してしまったため、借金を返しそびれ、返済の催促もありませんでした。しかし、2023年にEさんから「借金を返して」と申し出がありました。DさんはEさんに消滅時効を理由に借金は返さないと説明しましたが、個人間の借金の消滅時効は10年と旧民法が定めているため、Eさんが返しますといえば、借金返済の義務を負います。
出典:法務省【消滅時効に関する見直し】
借金の消滅時効が適用される条件
借金の消滅時効が適用される条件は以下の通りです。
- 「返済期日」か「最終返済日」から5年、または10年が経過している
- 時効の更新がない
- 債務者が借金のあることを認めていない
以下で、1つ1つの条件を詳しく解説していきます。
時効が成立していること(借金の消滅時効の期間経過)
借金の消滅時効は、改正前・改正後でも最長で10年です。
改正された民法の場合、2つの時効消滅期間のうち早いタイミングの時効期間が適用されるので、5年、もしくは10年が経過していることが条件です。
改正前民法の場合は、消費者金融や銀行が債権者となっている場合や、個人間の借金、住宅ローンなどが同じく5年、もしくは10年となっています。
つまり、2013年、もしくは2018年にできた借金は2023年中に時効が成立するので、消滅時効の対象です。
また、改正前民法だと1年から3年で時効になる借金もあります。
この場合、2023年にはすでに時効が成立しているので消滅時効の対象です。
債権者から裁判を起こされていない(時効の更新がされていない)
債権者は、債務者から借金を返してもらうためにさまざまな方法を取り、裁判はその代表的な手段です。
借金の返済が滞ると、債権者が裁判を起こします。
特に、住宅ローンを滞納した場合、金融機関は住宅を売って債権を回収するために、早い段階で裁判に踏み切るでしょう。
債権者が裁判を起こした場合、どのような判決が出ても時効の更新が行われます。
時効が更新されると新たにそこから5年、10年が経たないと消滅時効は成立しません。
改正前民法の場合は、1年、3年の場合もあるでしょう。
裁判以外にも時効が更新されるケースには、以下のようなものがあります。
- 財産の一部が差し押さえられた
- 債務者本人が借金の返済意思を示した
財産の一部を差し押さえられた場合、債務を一部返済したと考えられます。
また、返さないまでも債務者が「必ず返します」「もう少し待ってください」など返済の意志を示したり、債務承認書へサインしたりすれば、時効は更新されてしまうので注意しましょう。
なお、債務の一部返済は少額でも成立します。百円でも、千円でも支払ってはいけません。
銀行や消費者ローンは借金の消滅時効について豊富な知識があります。
そのため、時効を更新しようといろいろな手段を使ってくるでしょう。
借金があることを認めていない(債務の承認がされていない)
債務者自身が借金のあることを認めていない、というと奇妙に聞こえますが、これは個人間の借金や相続した借金が該当する可能性があります。
例えば、個人間の借金の場合きちんとした借用書ではなく、口約束などで借りる場合もあるでしょう。
そして、自分は確かに返したのに相手が返済していないと主張すると、トラブルに発展する可能性もあります。
また、「闇金」などといわれる違法な金融機関の場合、債務者の親族を勝手に連帯保証人にする可能性もあるでしょう。
例えば、離婚して長年音信不通だった両親が、違法な金融機関からお金を借り、勝手に連帯保証人にされていたなどのケースもあります。
このほか、親が個人間で借金をしており、それを誰にも伝えないまま亡くなって相続をすると、債務まで引き継いでしまいます。
その結果、知らない間に借金ができていたといったケースもあるでしょう。
このような場合、自身の借金と認めてしまうとその時点から改めて時効までの期間がスタートします。
なお、債務の承認とは債務者が認めないと成立しません。ですから、債権者が「借金を払うように」と手紙やはがきを送ったり電話をかけてきたりしても、成立しないので混同しないようにしましょう。
違法な金融機関の中には、なんとか自分の借金だと認めさせようとあの手この手で迫ってくる場合もあります。
借金の時効成立は難しい?非現実的なのか
今まで解説してきた内容を考えると、借金の時効成立は難しいように思えます。
特に、銀行をはじめとする金融機関から借金をした場合、「借金返済が難しくなったから、返済をやめて時効を待つ」というのは非現実的に思えるでしょう。
しかし、借金の消滅時効が成立した例はあります。特に、個人間の借金や自分でも知らない間に相続してしまった借金などは、消滅時効が成立する可能性があります。
ただし、自分で借金の消滅時効に関する一連の手続きを行うのはなかなか難しいでしょう。
弁護士など法律の専門家に相談するのがおすすめです。
特に、自分以外がした借金の返済を迫られている場合は、早めに相談しましょう。
自分の借金が時効かどうか調べる方法はある?
借金の消滅時効を利用したい場合、自分がどのくらいの借金をいつ行ったのか正確に把握する必要があります。
ここでは、自分の借金が時効かどうか調べる方法について解説します。
債権者からの郵送物から調べる方法
借金の返済を求める債権者から郵送物が送られてきている場合、それを調べれば借金をした日付や額、最後に支払いをした期日などがわかります。
最後に支払いをした日から5年、もしくは10年経っている場合は消滅時効が成立している可能性が高いでしょう。
債権者が「必ず払うと約束した」といっても、それを証明できなければ時効は成立します。
個人信用情報を取得する方法
個人信用情報とは、クレジットカードの使用履歴や借金の有無、借金の最終返済日などの情報の総称です。
「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」「日本信用情報機構(JICC)」「指定信用情報機関(CIC)」の3つの信用情報機関に管理されており、インターネットや郵送で開示請求ができます。
ただし、個人信用情報は、銀行や正規の消費者金融、クレジットカード会社からの借金しか記録されていません。個人間の借金や、違法な金融機関などの情報は取得できないので注意しましょう。
弁護士に依頼する方法
弁護士に依頼すれば、借金の時効を調べてもらったり債権者とのやり取りを代行してもらったりできます。
借金の消滅時効を利用して返済の義務から逃れたい場合は、できるだけ早く弁護士に依頼して必要な手続きを代行してもらいましょう。
なお、弁護士以外にも司法書士も借金の時効援用についての手続きを依頼できます。
ただし、司法書士の場合140万円を超える債務の時効援用手続きはできません。
特に、個人間や違法な金融機関とのやり取りを自分で行うと問題がこじれる可能性もあります。できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
借金問題に詳しい弁護士の中には、初回は無料で相談に乗ってくれるところもあります。
消滅時効で借金をなくすためには「時効の援用」という手続きが必要
借金を最後に支払ってから、5年もしくは10年を過ぎても時効は自動的に成立しません。
債務者が時効の援用を行う必要があります。
ここでは、時効を成立させて借金をなくすために必要な時効の援用について解説します。
時効の援用とは
時効の援用とは、「時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張すること」です。借金の消滅時効においては、債務者が債権者に「借金の消滅時効を迎えたので、借金をもう払いません」と宣言することです。
時効の援用ができるのは、「時効の完成により直接的に利益を受ける者」に限られるので、債務者、もしくは債務者の保証人になった者が手続きします。
例えば、親が債務者になっており、高齢などを理由に子どもが代理として時効の援用を主張することはできません。
ただし、時効の援用に関する手続きでは、弁護士をはじめとする法律家に依頼することはできます。
詳しくは「時効の援用とは?」でも解説しているので、併せて読んでみてください。
時効の援用のやり方
時効の援用のやり方は、それほど難しくありません。まず、確かに時効が成立していることを確認しましょう。
時効は、1分でも過ぎていれば成立します。
時効が確かに成立していることを確認したら、債権者に「時効援用通知書」を内容証明郵便で送ってください。
時効援用通知書の書式に特に指定はありませんが、以下の内容は必ず含めましょう。
- 債務者の住所・氏名
- 債権者の住所・氏名
- 時効援用通知書を記載した日付
- 時効の援用手続きを行う、といった内容の文章
- 借金を特定できる情報(借金をした日時・借入額、借金の契約番号など)
- 信用情報機関からの事故情報削除依頼
インターネットを検索すれば、文面の雛型も出てくるので参考にしてください。
なお、内容証明郵便は行数に一定の決まりがあります。
自分で作成する場合は日本郵便のホームページに書式のルールが書いてあるので参考にしましょう。
内容証明郵便が債権者に届いて債権者が確認すれば、時効の援用は成立します。
その後、債権者から「債務不存在証明書」が届けば、相手も時効の成立を認めたことになるので安心です。
時効の援用を債務者が行い、債権者が認めた時点で借金は返済義務がなくなります。
その後、債権者が「やはり借金を返して」と主張しても、それは違法です。
ただし、改めて計算した結果借金の時効が成立していないと分かった場合、債権者が裁判を起こせば時効が更新されてしまいます。
したがって、時効が確かに成立しているかどうかは入念に確認してください。
特に、2020年4月1日以降に借金をした場合は職業や種類によっては時効が伸びています。
時効の援用は自分でもできる?
時効の援用は自分でも可能です。しかし、文章を書くのに手間取ったり時効が確かに成立しているかの計算を間違ったりすれば、トラブルに発展する場合もあるでしょう。
特に、相手が業者の場合、何かと理由をつけて時効を認めない可能性があります。
このようなリスクを考えると、弁護士に手続きを代行してもらったほうがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、時効の計算なども間違えることはありません。また、万が一トラブルになった場合も法律の知識をもって対応してもらえます。
時効の援用の費用目安
時効の援用を弁護士に依頼した場合、「内容証明郵便費用」に加えて、相談費用や弁護士への依頼費用がかかります。
借金の時効の調査なども依頼した場合、その費用も上乗せされます。
相談費用や弁護士への依頼費用は法律事務所によって異なるので、ホームページなどで確認しましょう。
現在は、料金を明確に提示する法律事務所が増えています。
依頼費用の相場は、時効の援用のみならば数万円~10万円までです。
当事務所は、相場よりも費用を抑えて依頼人の負担を軽減すべく努力しています。
借金をなくすためには時効の援用か債務整理を弁護士に依頼するのが正攻法
借金が積み重なると、利息も膨らんで返済が大変になります。
また、親や兄弟が秘密の借金をしており、誰にも言わずに亡くなってしまった場合、気付かなければ債務まで相続してしまう可能性もあるでしょう。
借金のトラブルは一度こじれると解決が難しいうえに信用情報も傷がつきます。
信用情報に傷がつくと、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になり、住宅ローンを組んだりクレジットカードが新しく作れなくなったりします。
借金の相談や時効の援用は法律の専門家である弁護士に相談しましょう。手続き代行から債権者との交渉まで行ってくれるので、問題がスムーズに解決します。
なお、弁護士に相談すると費用がかかるというイメージがありますが、初回相談は無料であるところも多く、依頼する内容を絞れば費用も抑えられるでしょう。ひとりで悩まずにまずは相談してみましょう。
 時効の消滅時効に関するよくある質問
時効の消滅時効に関するよくある質問
最後に、消滅時効に関するよくある質問をご紹介します。消滅時効に関して疑問がある方は、まずはこちらを確認してください。
15年前の借金は時効の可能性が高いでしょうか?
15年前の借金は、一見すると消滅時効が成立している可能性が高いです。
ただし、時効の更新については注意しなければなりません。
時効の成立は、借金を最後に支払ってから5年~10年です。
15年前の借金でも3年前まで支払いを続けていた場合、時効の成立まで最低でも2年が必要です。
したがって、最後の支払いをした時期がいつなのか必ず確認しましょう。
分からない場合は、信用情報を確認するか弁護士に調査を依頼してください。
借金を20年間放置していた場合時効になっているのでしょうか?
借金を20年間放置していた場合、消滅時効が成立している可能性が高いです。
しかし、20年間借金が本当に放置できていたかどうか確認する必要があります。
20年前ならば債権者が債務者の家族に連絡をしており、家族が債務者の代わりに借金を支払っていたといった可能性もあるでしょう。
借金の消滅時効は最後に支払いをしてから5年、もしくは10年です。
20年借金の催促がなかったので時効が成立していると思っても、信用情報を確認するか弁護士に調査を依頼してください。
自分でも親や兄弟に確認してみましょう。
時効の援用が認められれば信用情報は回復しますか?
残念ながら、時効の援用が認められても信用情報は必ずしも回復するとは限りません。
これは、「時効成立」に関連する事故情報の取り扱いが、信用情報機関によって異なるためです。
時効の援用が認められれば借金も消えると考えている場合、事故情報も削除されます。
しかし、時効は成立しても借金をした事実は残ると考えている場合、「自然債務」扱いとなって、事故情報は残ります。
信用情報がどちらの説を取るのかは明確にされていないので、ケースバイケースとしかいえないのです。
また、時効の援用が成立する前に借金の返済が遅延していた場合、その情報が信用情報機関に記録されます。この遅延情報は、時効の援用が認められた場合も消えません。
ただし、永久に残るわけではないので、心配な場合は時効の援用が成立した場合、信用情報機関に問い合わせてみてください。