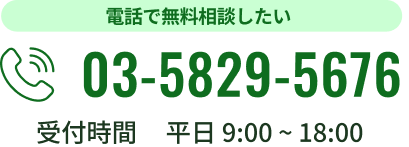時効の援用のやり方は?手続きの流れと時効援用通知書の書き方を解説
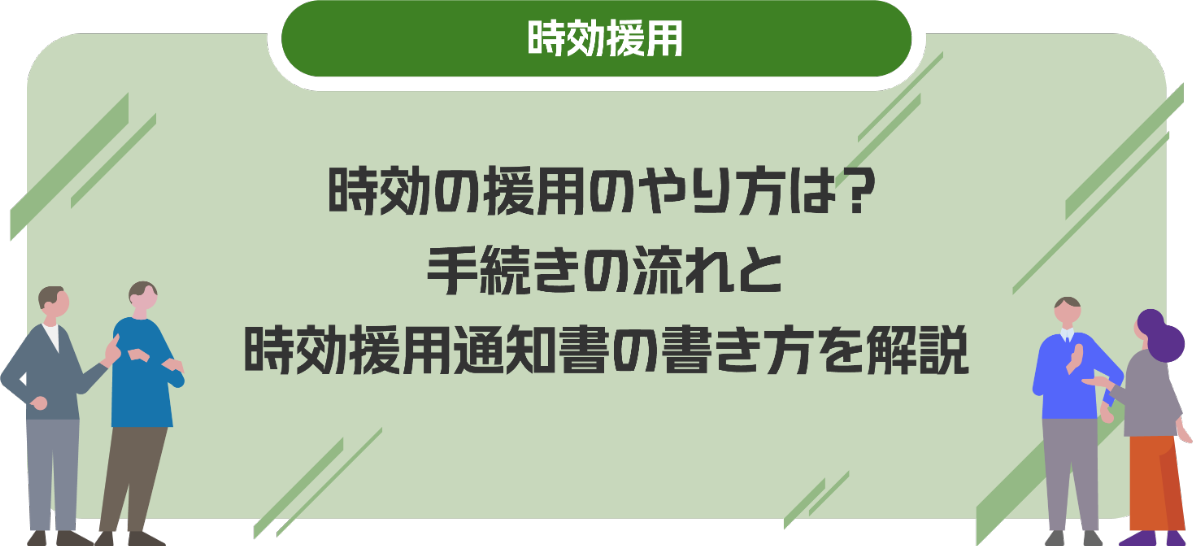
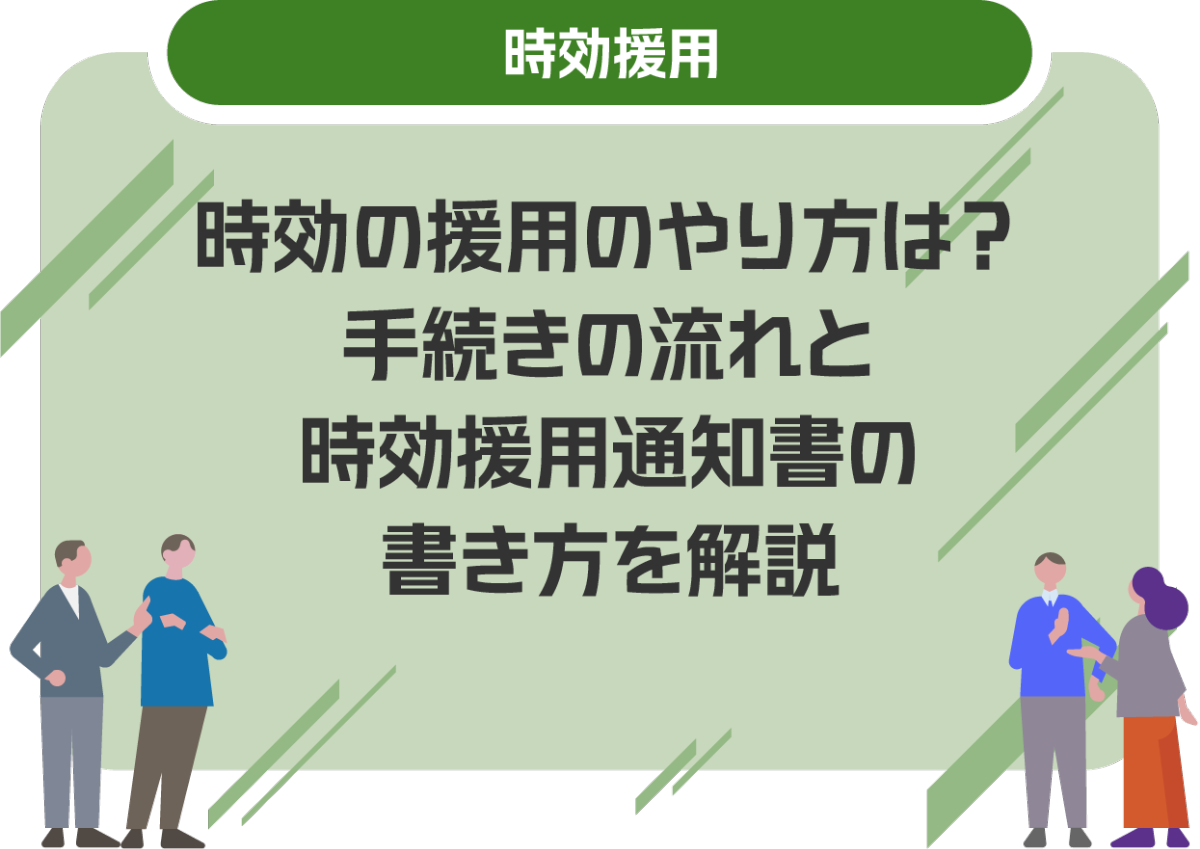
ただ、時効の援用と言われても馴染みない言葉ですし「具体的になにをすれば良いかわからない」と思ってしまいますよね。
そこでこの記事では「時効の援用のやり方」に焦点を当て、あなたが今後何をすべきかを明確に説明します。
時効の援用とは?借金を消滅させることができるって本当?
そもそも一番の関心事は「時効の援用をすると借金がなくなるのかどうか」ですよね。
結論、時効の援用に成功すれば、該当する借金の支払い義務はなくなります。では、時効の援用とはどんなものなのでしょうか。
時効の援用とは、債務者(お金を借りている側)が「借金が消滅時効を迎えたこと」を債権者(お金を貸している側)に主張する行為を指します。
その後、債権者が借金の時効を認めれば借金はなくなります。
また、借金の時効が完成する条件は以下3点です。
- 時効が成立していること(借金の消滅時効の期間経過)
- 債権者から裁判を起こされていない(時効の更新がされていない)
- 借金があることを認めていない(債務の承認がされていない)
時効の援用そのものに関する知識は以下の記事で詳しく解説しています。
時効の援用のやり方|自分でもできるの?
時効の援用のやり方自体は案外シンプルです。必要な情報を揃えるのにも資格等は必要ないため「自分で行うことも可能」ではあります。
時効の援用の手順【3ステップ】
- 時効が完成しているかどうか確認する
- 時効援用通知書を作成する
- 時効援用通知書を「内容証明郵便」で債権者に送付する
しかし、これから説明する手順のなかでは「不慣れな作業」や「専門知識」が必要な場面も出てきます。自分で時効の援用をしようとしている場合は特に注意を払ってください。
時効が完成しているかどうか確認をする
時効の援用をするうえで一番重要なのは「時効が本当に完成しているかどうか」です。借金の消滅時効は下記のように定義されています。
| 2020年4月以降の借金(債権) | 2020年4月以前の借金(債権) |
| 返済期限日から5年 | 返済期限日から5年または10年 ※商事債権、銀行以外が基本的に10年計算になります。 |
ただ、
「返済期限がいつか忘れてしまった」
「途中で支払いをしている可能性がある」
上記2パターンに当てはまる場合は、より慎重に消滅時効が完成しているか判断するようこころがけましょう。
具体的には「CIC,JCIC、全国銀行個人信用情報センター」いづれかの信用情報機関に情報開示請求を行い以下の項目を調べる必要があります。
- 契約年月日/貸付日契約日→5年(10年)以上経過しているか
- 出金日利用日→5年(10年)以上経過しているか
- 返済状況/異動参考情報
- 入金状況/入金日/最新支払日→5年(10年)以上経過しているか
それぞれの信用情報機関の情報開示請求は以下のリンクから利用できるのでブックマークをしておくことをおすすめします。
3社全てで情報開示をする必要はありませんが、10年を大幅に経過した借金に関しては登録情報が異なる場合があります。
「借りている金額が大きい」
「数十年前の借金だから記憶があいまい」
という場合には、CICとJCICの両方に問い合わせを行うのがベターです。
また「過去に裁判を起こされて時効の更新がされていないか」も合わせて確認しましょう。過去に支払督促や訴状が届いている場合、時効が更新されている可能性があります。
時効の更新がされていると「更新された時点から5年経過」しないと時効が完成しませんのでご注意ください。
<自分でやるのは自信がない方はこちらのお問合せフォームをご活用ください>
時効援用通知書を作成する
時効が完成していると判断できたら、債権者に送付する「時効援用通知書」を作成しましょう。
作成手順【簡易版】は以下の通りです。
- 送付先を記載する
- 時効の援用をする日付を記載する
- 債権を特定できる情報を記載する
- 消滅時効を援用する旨の3点を記載する
- 送り主(自分の情報・実印)を記載する
詳しい書き方については「時効援用通知書の書き方【自分で用意する場合】」にて説明していますので、送付方法を確認したうえで読み進めてください。
時効援用通知書を「内容証明郵便」で債権者に送付する
時効援用通知書が完成したら「内容証明郵便」を使って、債権者へ送付して完了です。
普通郵便ではなく、「内容証明郵便」で送る必要がある点に注意しましょう。理由は「いつ、誰に、どの書類を送付したか」を記録しておかないと、時効の援用をした証明がしづらくなってしまうからです。
必ず内容証明郵便でないといけないわけではありません。
しかし、普通郵便で送って債権者から「受け取っていない」と言われた際、自分が不利になってしまう可能性が高いため「内容証明郵便」の利用が一般的になっているのです。
内容証明郵便の利用料金は以下で決まるため、1通あたり1000円程度あれば事足ります。
基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金=利用料金
時効援用通知書の書き方【自分で用意する場合】
時効援用通知書と聞くと「記入方法のルール」がありそうですよね。実は、書式や記載項目の法規定はありません。
ただし「時効援用通知書」としての効力を十分に発揮させるためには以下の項目を盛り込むことを推奨いたします。
- 消滅時効援用通知書だとわかる題名
- 宛先
- 消滅時効を援用することの意思表示
- 借金の消滅時効が完成している旨
- 債権を特定できる情報
- 契約日
- 最終弁済日
- 残元金
- 作成日時
また「債権を特定できる情報」とは、具体的に以下の情報を指します。
| 債権者(法人の場合) | 名称・住所 |
| 債権者(個人の場合) | 氏名・住所 |
| 債務者 | 氏名・生年月日・住所・会員番号 |
| 債権 | 債権の性質・金額・発生時期・最終返済日 |
<貴事務所の通知書テンプレートをPDFで挿入していただきたいです。>
時効援用通知書の書式は?
時効援用通知書は書式による制限はありません。しかし「内容証明郵便」には以下文字数の規定があるため
- 縦書きの場合:1行につき20文字以内・26行
- 横書きの場合:①1行につき20字以内・26行まで②1行につき13字以内・40行まで③1行につき26字以内・20行まで
いずれかに当てはまる必要があります。
手書きでも問題ありませんが、修正等のしやすさを加味してパソコンで作成することをおすすめします。
書式設定で上記条件に当てはまるよう設定してしまえば、あとは1枚におさまるように書類作成すればOKです。
時効援用通知書を書く際の注意点
注意すべき項目は多くなく、記入項目に漏れや誤植がないようダブルチェックをすれば基本的に問題ありません。
ただし、時効援用通知書は「同じ文書を3部(債権者送付用と郵便局保管用、差出人の控え)」用意する必要がある点には注意しましょう。
時効援用通知書の郵送方法
時効援用通知書を「内容証明郵便」で送る際の手順は以下の通り。
- 時効援用通知書を3部印刷する
- 郵便局に行き「内容証明郵便」で送りたい旨を伝える
- 郵送代金を支払い、控えを受領して完了
特に難しい点はありませんので安心してください。
時効援用通知書を送った後に必要な対応は?
時効援用通知書を郵送したら自分で何かをする必要はもうありません。
債権者側が裁判等を起こさない場合、借金は消滅します。
しかし、借金が消滅しても債権者から「借金の時効を認めます」といった報告がないケースがほとんどのため「本当に借金がなくなったのかな?」と不安に感じてしまう人も多くいます。
とはいえ、相手方(債権者)への連絡はハードルが高いですよね。そんなときは「送付から1ヶ月以上経過してから」信用情報を開示してみましょう。
CICに問い合わせて、残高は「0」:終了状況は「完了」:保有期限「5年後の日付」となっていれば成功しています。
借金が消滅したかどうか不安な人はプロ(弁護士)に依頼をしよう
今回は時効の援用のやり方を解説しました。読んでいて「本当に自分でできるのかな」と不安に思ってしまった人もいるかと思います。
たしかに、弁護士への依頼と聞くと「多くのお金がかかる」というイメージをお持ちかもしれません。
しかし、当事務所では時効の援用を以下の料金形態で承っています。
- 時効の援用 1件 税込み24,000円
- 内容証明 1通 税込み 4,000円
弁護士に依頼することで、以下の精神的・時間的メリットも生まれますので一度ご検討いただければ幸いです。
- 調査・書類作成の手間が省ける
- 相手方と直接やり取りをしなくて済む
- スムーズに時効の援用をすることができる
- 「借金が消えたかどうか」がはっきりわかる
 時効の援用(やり方・書き方)に関するよくある質問
時効の援用(やり方・書き方)に関するよくある質問
時効の援用を自分でやると失敗する可能性が高いですか?
可能性は高くはありません。しかし、万が一「失敗した場合」のデメリットもかなり大きいため、借金額が大きい場合は専門家へ依頼することをおすすめします。
時効の援用を弁護士に依頼する場合、費用はいくらくらいかかりますか?
費用相場は1社あたり3万円〜5万円程度が多いようです。当事務所では相場よりも安価で対応しています。(1件あたり24,000円+内容証明4,000円)
時効の援用からどれくらいで信用情報の回復しますか?
明確な規定はありませんが1ヶ月〜3ヶ月程度を見積もっておけば問題ないと思いますが、必ず信用情報が回復(ブラックリストから削除)されるとは限りません。
また、「時効の援用をした債権者以外にも債権者がいる場合」は回復されないので注意しましょう。