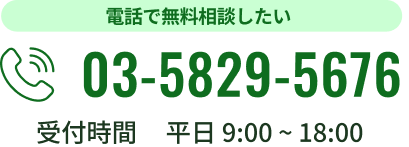時効の援用に失敗してしまうとどうなる?失敗例やその後にとるべき対応を解説
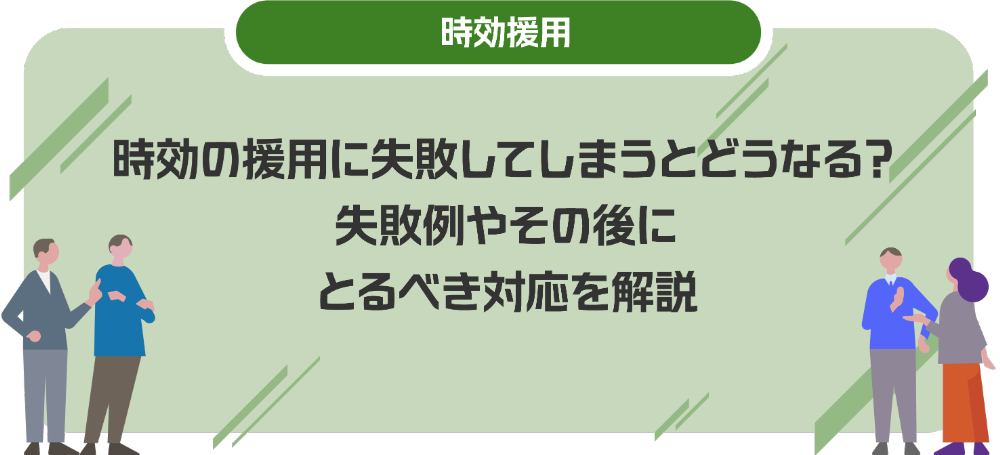
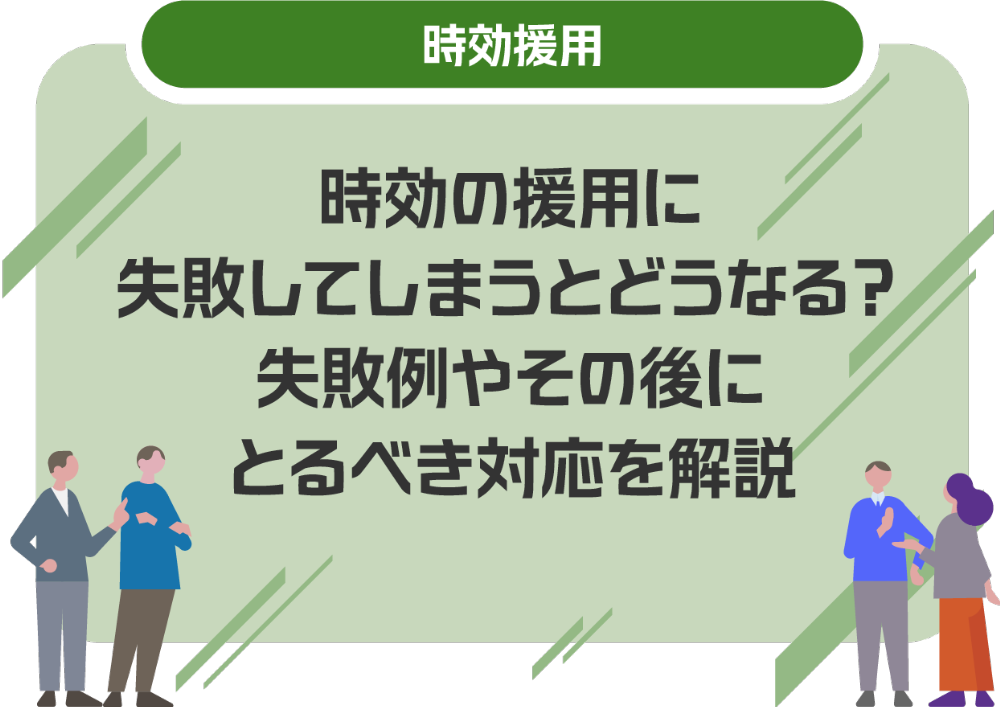
この記事では、時効の援用を考えている方に向けて、時効の援用は自分でできるのか、失敗した際のリスク、失敗した場合の対処法などを解説します。ぜひ、参考にしてください。
時効の援用に失敗してしまうとどうなる?
時効の援用に失敗したらどうしよう、どんなリスクがあるのかなど、時効の援用に関する不安を抱えている方も多いでしょう。時効の援用に失敗することで起こりうるリスクは以下の2点です。
- 支払い義務が発生する(元金+利息+遅延損害金)
- 時効のカウントが0からになってしまう
特に、一括払いでの請求になると支払わなければいけない額が高額になり返済が困難になるケースが多いです。そのため、時効の援用を行う際には慎重に行いましょう。以下では、それぞれのリスクについて詳しく解説します。
支払い義務が発生する(元金+利息+遅延損害金)
時効の援用に失敗すると借金の時効が認められなくなるため、支払い義務が発生します。時効の援用に失敗した場合、元金と利息だけではなく遅延損害金も上乗せされます。遅延損害金とは、債務者が借金の返済を滞納した際に債権者にかかった損害を賠償するために支払うものです。遅延損害金は返済の遅延・滞納をした期間が長ければ長いほど金額が大きくなるため、借金の時効を迎えるほどの期間返済していない場合には、元金の2倍ほどに膨れ上がっているケースも珍しくありません。
業者によっては、元金とこれまでの利息、遅延損害金をまとめて、一括での返済を請求してくるケースもあります。一括払いだと経済負担が大きく、支払えないという場合もあるでしょう。交渉次第では分割払いにできる可能性もありますが、分割払いに応じてくれるかどうかは業者によって異なり、必ず分割払いにできるわけではありません。金銭的余裕がなく一括での返済が難しい場合には、債務整理を行わなければいけなくなる可能性もあります。債務整理を行うには手間や費用がかかるため、このような方法を避けるためにも時効の援用を失敗しないように慎重に行うことが重要です。
時効のカウントが0からになってしまう
時効の援用に失敗してしまうと、時効がリセットされます。借金には時効があり、永久的に返済義務が残り続けるわけではありません。借金の時効は原則として5年と決められており、最終借り入れまたは最終返済日から5年を経過することで時効が成立します。
ただし、時効の援用に失敗すると「時効のカウントは0になる」ため注意しましょう。たとえば、数え間違えており時効成立まであと3カ月という時点で時効の援用をしたとしましょう。この場合、まだ時効は成立していないため、そもそも時効の援用ができません。失敗したら3カ月待って再度時効の援用をすればよいと考える方もいるかもしれませんが、時効の援用に失敗した時点で時効はリセットされます。リセットされた時点から5年経過しなければ時効は成立しません。そのため、時効の援用に失敗することで借金が消滅するまでの期間が伸びてしまい、長期間借金をしている状況が続いてしまいます。
時効の援用に失敗してしまう原因は何がある?
時効の援用に失敗してしまう原因としては、以下の4つの原因が挙げられます。
- 借金の時効が成立していない
- 過去に裁判を起こされている/裁判上の手続きがなされている
- 時効成立後に支払いの約束を取り付けてしまった
- 時効援用通知書に不備があった
このように、自己判断で時効の援用を行ったことによるミスが主な原因です。ここからは、それぞれの原因について詳しく解説するので、参考にしてください。
借金の消滅時効が成立していない
前述したとおり、借金には時効があります。しかし、自己判断で借金の消滅時効が成立していると判断してしまうのは危険です。
借金の消滅時効は、最終支払日から5年経過しなければ成立しません。長期間借金をしている場合、最後に支払ったのがいつなのか覚えていないというケースもあるでしょう。また、時効の起算日を間違えて計算してしまい、時効が成立したと勘違いしてしまうケースも少なくありません。時効の起算日とは、時効がスタートする時点のことです。借金の場合には、最終返済日の次の日が起算日となります。「おそらく〇年〇月ぐらいが最後だろう」とあいまいな記憶のまま時効の援用をしてしまうと、実際には時効の成立まではまだ期間があり、時効の援用に失敗してしまうという場合があります。
また、裁判を起こされており敗訴しているといったケースでは、時効が伸びてしまいます。時効は判決の確定から10年に伸びるため、裁判があった場合には注意が必要です。このように、時効が成立していると自己判断したものの、実際には時効が成立しておらず失敗するというケースも多いようです。
過去に裁判を起こされている/裁判上の手続きがなされている
過去に裁判が起こされている場合も注意しなければなりません。債権者によって訴訟が起こされた時点で、時効はストップします。裁判を起こされた時点で時効までの期間が残り1カ月となっており裁判中に1カ月が経過したとしても、訴訟により時効はストップしているため時効成立とはなりません。また、裁判に敗訴して判決が確定した場合には時効はリセットされ、確定時点から10年経過しなければ時効は成立しないのです。確認しておきましょう。
知らない間に裁判を起こされており敗訴しているといったケースもあります。訴状が届いていたのに忘れてしまった、同居家族が訴状を受け取り知らせてくれなかった、住民票を移し忘れていて音信不通になっていたなど、知らない間に裁判を起こされている場合も珍しくありません。時効が成立したと思い時効の援用をしたら、知らない間に敗訴が確定しており時効が延長されていたというケースもあるようです。
また、裁判が起こされていなかったとしても、裁判上の手続きが行われていたというケースもあります。たとえば、債権者が裁判所を通して借金の催告や返還請求などを行った場合です。裁判上の手続きが行われた時点で時効がストップするため注意しましょう。その後、訴訟が起こされ敗訴した場合には、時効はその時点から10年になります。
時効成立後に支払いの約束を取り付けてしまった
時効が成立していたとしても、債権者に対して支払いの意思を見せると時効がリセットされてしまいます。借金は原則として最終返済から5年で時効を迎えますが、特定の出来事があると時効がリセットされて、再度0からのスタートとなります。時効が更新される事柄は以下のとおりです。
- 債権の差押え、仮差押え、仮処分
- 訴訟、支払督促を起こされる
- 債務の承認
時効成立後に支払いの約束を取り付けるという行為は、債務の承認にあたります。債権者に対して借金があることを認めたということになり、その時点で時効が成立していたとしてもカウントがリセットされ、時効は債務の承認をした時点から5年に延長されます。この際、「支払います」と明確に伝えていなくても、返済スケジュールの相談や分割払いの相談など返済する意思を見せてしまうことで、債務の承認とみなされるケースもあるようです。業者の中には時効が成立していることを知りながら、支払いの約束を取り付けて時効をリセットさせようという業者もいるため、注意しましょう。
時効援用通知書に不備があった
時効の援用をする際には、債権者に時効援用通知書を送付します。時効援用通知書は自分で作成することも可能ですが、不備があった場合には時効の援用ができない可能性もあるため注意しましょう。時効援用通知書によくある不備は以下のとおりです。
- 記載すべき事項に漏れがある
- 債権を特定する記載が不足している
- 内容証明郵便ではなく普通郵便で送ってしまった
時効援用通知書には記載しなければいけない事柄が定められており、記載事項が不足していると時効の援用が認められないケースがあります。記載すべき事項は以下のとおりです。
- 時効を援用する日付(書類の作成日もしくは発送日)
- 相手の社名、住所
- 差出人の氏名、住所、生年月日
- 債権を特定する情報
- 消滅時効が成立している旨
- 時効を援用するという旨
基本的にはこれらの事項を漏れなく記載することが重要です。特に、時効を援用する意思表示をしっかりと記載しなければ、時効援用通知書をして機能しません。そのため、時効を援用する旨は忘れずに記載しましょう。
どの債権に対して時効の援用をするのか明確にする必要があるため、債権内容を特定する情報を漏れなく記載することも重要です。たとえば、「借り入れ日」や「借入金額」、「最終返済日」、「契約番号」などです。特に複数の借金がある場合には、どの借金に時効の援用を適用するのか特定しなければ、時効の援用として認められない可能性もあります。
時効援用通知書は内容だけではなく、送付方法も重要です。基本的には配達証明付きの内容証明郵便で送付しましょう。内容証明郵便とは、「誰が、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるものです。普通郵便だと送ったという証拠が残りません。そのため、時効援用通知書を送った、受け取っていないという水掛け論になる可能性があります。そのため、文書の内容や誰がいつ誰に送ったかを証明できる、内容証明郵便で送付しましょう。
時効の援用でよくある失敗例
ここでは、時効の援用でよくある失敗の具体例を紹介します。
自分で時効の成立を判断したが、実は成立していなかった
- 性別、年齢:男性、48歳
- 借りていた金額:80万円
- 状況:7年前に借金をし、2年間は支払ったがその後支払いが厳しくなり放置していた
- 失敗の原因:最終返済日を明確に覚えておらず時効の起算日を間違えていた
時効は最終返済日から5年が経過することで成立します。しかし、この男性のケースでは、最後に支払ったのがいつなのかを明確に覚えておらず、「大体5年は経っただろう」と思い、時効の援用を行ってしまいました。しかし、実際には時効まであと2カ月残っており、時効の援用に失敗してしまったというケースです。
気づかないうちに債権者が裁判上の手続きや裁判をしていた
- 性別、年齢:女性、39歳
- 借りていた金額:150万円
- 状況:引っ越しを繰り返しており、住民票を実家のままにしていた
- 失敗の原因:住民票を移しておらず音信不通状態のまま、裁判の判決が確定してしまった
知らないうちに裁判が起こされ敗訴が確定していたケースです。借金の時効は裁判上の手続きや訴訟を起こされることでストップし、敗訴が確定すると時効は判決の確定から10年となります。この女性の場合引っ越し時に住民票を移さなかったため音信不通状態となり、裁判所からの訴状も確認できない状態でした。本人が気づかないうちに裁判が行われて判決が確定していたため、時効が10年に伸び時効の援用に失敗してしまったというケースです。
時効の援用に失敗してしまった場合の対処法
時効の援用に失敗してしまった場合には、弁護士などの専門家に依頼しましょう。弁護士に依頼することで、債権者からの取り立てや督促をストップできたり、債務整理の相談などができたりします。また、過払い金があるかどうかの確認や、債権者との交渉なども代行してくれます。
時効の援用が失敗し支払いが困難な場合はどうしたらよい?
時効の援用に失敗してしまったが、金銭的な余裕がなく支払いが難しいというケースも珍しくありません。支払いが難しい場合には、以下の2つの手段を取ることが考えられます。
- 弁護士に依頼をして「分割払い」ができないか交渉してもらう
- 債務整理を行う
時効の援用に失敗した場合の対処法は主に2つですが、このような状態にならないためには「失敗を防ぐこと」が重要です。時効の援用に失敗しなければ、さらなる経済負担や精神的な負担を負うこともないため、まずは時効の援用を失敗しないような対応を心がけましょう。
弁護士に依頼をして「分割払い」ができないか交渉してもらう
まずは、弁護士に依頼をして「分割払い」ができないか交渉してもらいましょう。業者の中には一括での支払いを求めてくるケースもあります。しかし、元金と利息に加えて遅延損害金も支払わなければいけないため、一括で支払うとなると多くのお金が必要になります。まとまったお金を用意できないというケースも多いでしょう。その場合には、分割払いができないかといった和解交渉を弁護士に行ってもらう方法があります。
分割払いに応じてくれるかどうかは業者によって異なりますが、一般的には応じてくれるケースが多いようです。分割払いの場合には、遅延損害金も含めた金額を分割で支払うことになります。また、和解後から完済するまでに発生する遅延損害金は免除されるため、新しく遅延損害金が発生することはありません。
債務整理を行う
債務整理を行う方法もあります。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産という3つの種類があり、それぞれにメリット・デメリットが異なります。それぞれのメリット・デメリットを表にしてまとめました。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 任意整理 | 金利引き直しや借金の減額などができ、3~5年での分割払いができるため月々の返済負担が軽くなる。 これまでの遅延損害金や今後発生する利息などがカットできる可能性がある。 | 信用情報に事故情報として登録される。 安定した収入がなければ返済計画が立てられないため、任意整理できないケースも。 原則として元金を減らすことはできないため、個人再生・自己破産よりも返済額は多くなる。 |
| 個人再生 | 裁判所に返済困難であることを認めてもらって借金の減額ができる。住宅などの高価な財産を維持しながら借金の整理が可能。 | 信用情報に事故情報として登録される。 手続きに手間がかかり費用がかかる。 保証人がついている場合には、保証人に返済の請求がされる。 |
| 自己破産 | 財産がないことを裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払い義務を免除してもらえるため、借金が0になる。 | 信用情報に事故情報として登録される。 職業や資格に一定の制限がある。 生活に必要な家財道具など以外の財産を処分する必要がある。 保証人がついている場合、保証人に返済の請求がされる。 |
時効の援用に失敗しないためのポイント
時効の援用に失敗しないためには、しっかりと借金の状況を把握することが重要です。たとえば、最終返済日がいつなのか、裁判を起こされていないかなど、時効の援用が成立する上で重要なポイントについては、きちんと調べなければいけません。しかし、信用情報の照会や裁判の有無などを自分で調べるのは困難です。
そのため、時効の援用を成功させたい場合には弁護士に依頼するとよいでしょう。弁護士に依頼する際には、依頼費用がかかります。そのため、費用をなるべくかけたくないからと自分で時効の援用を行いたいと思っている方も多いでしょう。借金の金額と弁護士のへの依頼費用を天秤にかけて、どちらの方が「今後の自分にメリットがあるのか」を考えることが大切です。また、時効の援用に失敗してしまうとさまざまなリスクがあるため、起こりうるリスクと弁護士への依頼でかかる費用を比較して検討するとよいでしょう。
山本綜合法律事務所は、業界最安水準で時効の援用ができます。時効の援用にかかる費用は24,000円+内容証明4,000円となっており、追加料金や成功報酬は一切かかりません。費用を抑えながら時効の援用手続きを任せられるため、金銭的に不安がある、費用をあまりかけずに時効の援用をしたいという方にもよいでしょう。
まとめ
時効の援用は自分で行うこともできますが、時効が成立しているかどうか、裁判が起こされていないかなど、しっかりと調べてから行わないと失敗するリスクが高くなります。時効の援用に失敗することで経済負担、精神的負担が大きくなるため、失敗しないことを重視しましょう。時効の援用を成功させるには、弁護士などのプロに依頼するのがおすすめです。弁護士なら、時効が成立しているか、裁判の有無などをしっかり調べた上で時効の援用ができるかどうかを判断してくれるため、失敗するリスクを最小限にできます。
山本綜合法律事務所は、業界最安水準で時効の援用を請け負っています。かかる費用は全部で28,000円となっており追加料金や成功報酬はかかりません。リーズナブルに時効の援用ができるため、「放置していた借金を清算したい」、「費用をかけずに時効の援用を成功させたい」という方は、お気軽にご相談ください。