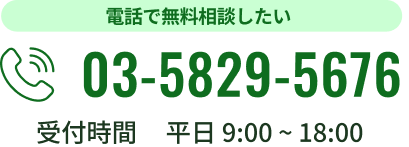時効の援用通知書を自分で書く場合のポイントと注意点をわかりやすく解説
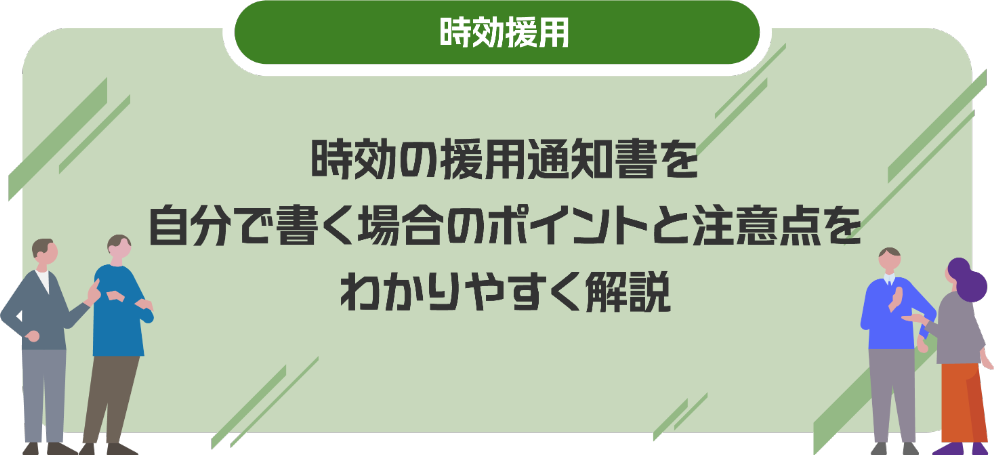
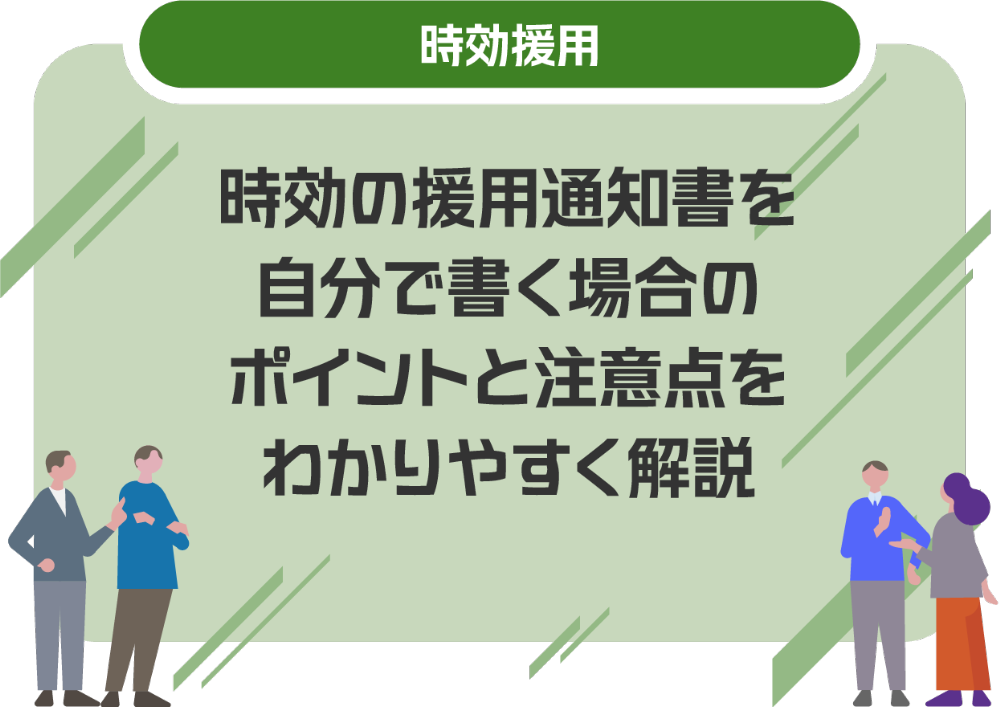
ただ「時効の援用を弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのはお金がかかりそう」と思い、自分で時効の援用ができないものかと調べている人も多いと思います。
この記事では、時効の援用のポイントである「時効援用通知書」を自分で書く場合の手順を解説します。
【要点まとめ!時効援用通知書を自分で書く手順】
1.借金の消滅時効が完成していることを確認します。
2.通知書の作成日付を記載します。
3.相手方の氏名、住所を記載します。
4.自分の氏名、住所、生年月日を記載します。
5.時効援用を主張する旨を記載します。
6.時効の期間を記載します。
7.今後、相手方からの請求を一切受け付けない旨を記載します。
8.署名捺印します。
9.内容証明郵便で送付して完了です。
時効の援用で借金を無くすためには時効援用通知書を作成する必要がある
借金が時効を迎えても自動で借金が無くなるわけではありません。今回のメインテーマである「時効の援用」をして初めて借金がなくなります。
そして、時効の援用をするために必須なのが「時効援用通知書」ということです。時効の援用の基本知識に関しては「時効の援用とは?」で解説しています。
「そういえば、まだ時効の援用がどんな権利・制度なのか曖昧だな」と思った人は、合わせて読んでみましょう。
関連記事:時効の援用とは?
時効援用通知書は自分で書いても問題ない?
時効援用通知書という小難しい名前から「自分で作成はできないのかな、有資格者に作成を頼まないといけないのかな」と疑問に思う人もいらっしゃると思います。
結論、時効援用通知書は「自分で書いても問題ありません」。特別な資格も必要なく、内容に不足がなければ有効な書類として機能します。
しかし、消滅時効に関する法的知識がない方が作成するのは少々リスキーであることには代わりありません。
「本当にこのフォーマットで合っているのかな」
「不足項目があったら時効が伸びてしまうのではないか…」
という不安がつきまとうこともしばしば。もし、不備があったり、時効が実は完成していなかった場合、時効の援用に失敗し「遅延損害金の請求」をされてしまう可能性もあります。
関連記事:時効の援用に失敗したらどうなる?
確実に時効の援用を成功させたい場合は、弁護士をはじめとした専門家に依頼したほうが無難です。
当事務所の場合は追加料金なしの「28,000円/1社」で対応しているため、依頼ハードルはかなり低くなっています。
関連記事:時効の援用の費用相場は安い?
時効援用通知書を自分で書く場合の手順
それでも、弁護士に依頼するお金を捻出するのは難しい、自分で書きたいというケースもあると思います。
この章では「時効援用通知書を自分で書きたい場合の手順」を解説します。
細かい注意点も合わせて説明しているので、通知書を作成する際は記事と照らし合わせながら作成するよう心がけましょう。
大まかな、時効援用通知書の作成手順は以下の3ステップです。
- 時効の完成を確認する
- 時効援用通知書を作成・印刷する
- 時効援用通知書を内容証明郵便で送付する
それでは、各ステップでのポイント・注意点を見ていきましょう。
時効が完成しているかを事前確認する(信用情報機関への情報開示請求)
まず、借金の消滅時効が完成しているか確認しましょう。
借金の契約書が手元にあり、返済期日が明らかな場合は、返済期限から「5年または10年経過しているか」を確認しましょう。
返済期日から5年または10年と記載したのは、借金の契約年月日によって「時効の期間が異なるから」です。
| 2020年4月以前の借金 | 2020年4月以降の借金 |
|---|---|
| 時効10年または5年 ※10年の例:貸金業者・消費者金融、信用金庫住宅ローン ※5年の例:商事債権(商人同士の取引によって生じた債権)、銀行 | 5年 |
なかには「借金の返済期日や最終支払日が分からない」という方もいると思います。その場合は、CICやJICCといった「信用情報機関」に情報開示請求を行いましょう。
- 契約年月日/貸付日契約日→5年(10年)以上経過しているか
- 出金日利用日→5年(10年)以上経過しているか
- 返済状況/異動参考情報
- 入金状況/入金日/最新支払日→5年(10年)以上経過しているか
上記4項目をチェックして時効の完成がされているか確認して「完成している」と判断できれば書類の作成に移ります。
ただし「過去に裁判を起こされていたり、時効の延長がされているかどうか」を調べることができない点は注意が必要です。
時効援用通知書のテンプレートに沿って記入事項を埋める
実は、時効の援用に失敗してしまう要因のほとんどが「時効が完成していなかった」というケースです。
言い換えれば難しいのは「時効の完成がされているかどうかの判断」であって、時効援用通知書の作成ではありません。
ですから、書類作成自体は気負いせず「こういう項目を記入すればいいのね」と確認できればOKです。
時効援用通知書には以下の項目を入れ込むようにしましょう。
- 消滅時効援用通知書だとわかる題名
- 宛先
- 消滅時効を援用することの意思表示
- 借金の消滅時効が完成している旨
- 債権を特定できる情報(債権者の氏名・住所・契約日・返済期限等)
- 契約日
- 最終弁済日
- 残元金
- 作成日時
<時効援用通知書のテンプレを挿入してください>
時効援用通知書の書き方における注意点
時効援用通知書の作成で気をつけたいのは以下3点です。
作成が難しくないとはいえ、内容に不備があると失敗リスクが大きくなってしまうため、念入りに確認するようにしましょう。
- 内容証明郵便の書式は守る必要がある
- 送付前に控えを2枚(合計3枚)用意する
- 間違いを訂正する場合は訂正印を押す
内容証明郵便の書式は守る必要がある
まず、時効援用通知書は「確かに送付をしたこと」を証明するために「内容証明郵便」で送る必要があります。
また、内容証明郵便の場合は以下フォーマットを遵守する必要があるため、書類作成をする際はフォーマットの設定を必ずするようにしてください。
- 縦書きの場合:1行につき20文字以内・26行
- 横書きの場合:①1行につき20字以内・26行まで②1行につき13字以内・40行まで③1行につき26字以内・29行まで
wordの場合は、以下の手順で設定できます。
【行数を指定する】
- 行数を指定するテキストを選択します。
- [ホーム]タブの[フォント]グループで、[行間]ボックスのドロップダウンメニューをクリックします。
- 行数を選択します。
【文字数を指定する】
- 文字数を指定するテキストを選択します。
- [ホーム]タブの[フォント]グループで、[文字数]ボックスのドロップダウンメニューをクリックします。
- 文字数を選択します。
送付前に控えを2枚(合計3枚)用意する
内容証明郵便の場合は、送付する原本とは別に「郵便局、自分」で保管するための控えが2枚必要です。
時効援用通知書は「3枚」印刷する必要があると覚えておきましょう。
間違いを訂正する場合は訂正印を押す
公的文書全般に共通していますが、もし手書きで作成していてミスをした場合には「訂正印」を適切に使いましょう。
- 間違いの箇所に二重線を引く
- 間違いの箇所または近くに訂正印(捺印)をする
- 二重線を引いた上または周辺に「修正事項」を記載する
時効援用通知書が完成したら内容証明郵便で送付して完了
あとは、郵便局に行き「内容証明で送りたい」と伝えればOKです。内容証明郵便の費用は以下の通り。最も安くて959円で送ることができます。
- 一般書留の加算料金:通常435円
- 内容証明の加算料金:440円
- 重さに応じた基本料金:84円〜
郵送後は「控えを無くさない」ようにしておけば問題ありません。
時効援用通知書を送付した後「自分で確認すべきこと」はある?
「時効援用通知書は送ったけど、何も連絡がないんだが…」
なんとなくのイメージで時効の援用が成立したら「成立しました!」という知らせが届きそうですよね。
しかし、時効の援用が成功しても債権者から連絡があることは稀です。あったとしても「不要になった契約書の返送」程度です。
では、どうやって時効の援用が出来たか判断するかというと「信用情報機関に開示請求をして事故情報が消えていることを確認する方法」をとります。
電話で債権者に問い合わせる方法もありますが、電話を通じて「債務の承認」と取れる発言をしてしまうと、時効の援用に失敗してしまうリスクが伴います。
ですから、3ヶ月ほど空けてから信用情報の開示を行う方法がおすすめです。
もし、債権者から電話等の連絡が合った場合はその場で回答しないようにして、弁護士などの専門家に相談し「借金をなくす機会」をつぶさないよう注意しましょう。
まとめ
時効の援用通知書は紹介の通り「自分でも作成可能」です。しかし、確実に時効の援用を成功させたい、失敗して債務が増えるのは嫌だという場合は、弁護士に相談するのがおすすめ。
たしかに、費用はかかります。しかし、費用負担以上に「確実性の向上、不安の解消、精神的ストレスの減少」などのメリットが得られるのも事実。
3万円程度の予算がある場合には、当事務所に無料相談いただければ幸いです。時効が成立している可能性が高い場合は、最初から最後までしっかりとサポートいたします。